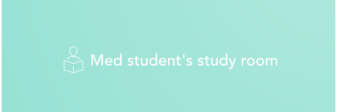「いつもの頭痛だと思っていたら、実は命に関わる病気が隠れていた―」
そんな事態を防ぐために、私たちは何を問診し、どこを診察し、どのように鑑別していけば良いのでしょうか?
本記事では、片頭痛や緊張型頭痛といった一次性頭痛から、くも膜下出血や動脈炎などの二次性頭痛まで、見逃してはいけないポイントを体系的に整理します。
OSCE(客観的臨床能力試験)や日常診療における頭痛評価のスキルアップに役立つ内容を、問診・身体診察・検査のステップで具体的に解説していきます。
この記事で身につくこと(3つ)
- 一次性頭痛(片頭痛・緊張型など)と二次性頭痛を見分ける力がつく
- Red flag(SNOOP)や身体所見をもとに、危険な頭痛を見逃さず対応できるようになる
- OSCEや実臨床でそのまま使える、問診・身体診察のコツと英語表現を身につけられる
導入症例:この患者、ただの片頭痛でしょうか?
🪪 Doorway Information
32歳女性/主訴:頭痛/バイタル:T 36.8℃, BP 116/74 mmHg, HR 72/min, SpO₂ 98%, GCS 15
🗣 患者の言葉
「ここ2〜3日、左側の頭がズキズキして…光が眩しくて吐き気もして、横になってても辛いんです。
でも以前から肩こりもあるし、寝不足だからかもって思ってたんですけど…」
一見すると片頭痛のようにも見えますが、本当にそうでしょうか?
それでは、頭痛を診るときの基本的なアプローチを整理していきましょう。
どう考える?頭痛診療の基本は「Primary vs Secondary」
この患者さんの訴えは「片側性」「ズキズキする」「光が眩しくて吐き気もある」――
いかにも片頭痛(migraine)を思わせる典型的な症状です。
しかし、私たちはまず「本当にこれは一次性頭痛(primary headache)なのか?」という視点で考えなくてはなりません。
一次性頭痛(片頭痛、緊張型、群発頭痛など)は症状そのものが疾患であり、重篤な基礎疾患を伴いません。
一方で二次性頭痛は他の病気が原因で引き起こされた頭痛であり、見逃すと命に関わる疾患が隠れている可能性があります。
そこで、最初に確認すべきはRed Flag(危険な兆候)です。
Red Flagを見逃さない:「SNOOP」でチェック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| S:Systemic signs | 発熱、体重減少、癌や免疫不全の既往 |
| N:Neurologic signs | 麻痺、複視、けいれん、意識変容 |
| O:Onset | 突発性発症(thunderclap headache) |
| O:Older age | 50歳以降の初発頭痛 |
| P:Pattern change | 性質・頻度の急変、進行性、初めての頭痛 |
この中で一つでも当てはまれば、二次性頭痛を疑って検査を検討する必要があります。
時間経過にも注目しよう
頭痛の鑑別は、「いつ・どれくらいでピークに達したか」も非常に重要です。
- 急性:くも膜下出血、髄膜炎、緑内障など
- 慢性:片頭痛、緊張型、脳腫瘍、副鼻腔炎など
- 再発性:片頭痛、群発頭痛など
特に「突然激しくなる頭痛(thunderclap)」は緊急疾患の兆候であり、即時CTが必要です。
部位別の頭痛の手がかり
| 部位 | 代表疾患 |
|---|---|
| 前頭部・片側性 | 片頭痛 |
| 後頭部・両側性 | 緊張型頭痛 |
| 眼窩周囲 | 群発頭痛、緑内障、副鼻腔炎 |
| 側頭部(高齢) | 側頭動脈炎(GCA) |
見逃してはいけない「まぎらわしい」疾患たち
- くも膜下出血(SAH)
- 側頭動脈炎(GCA)
- 脳腫瘍
- 髄膜炎
- 緑内障
- 高血圧性脳症
- 一酸化炭素中毒(冬、家族性頭痛)
🧱 Column|冬に家族全員が頭痛?一酸化炭素中毒を疑おう
CO(一酸化炭素)は無色・無臭・無刺激性で、不完全燃焼によって発生します。
特に冬の閉め切った室内+暖房使用という条件では、中毒のリスクが高まります。
CO濃度と症状の関係
| CO濃度(ppm) | 曝露時間 | 症状 |
|---|---|---|
| 50 ppm | 数時間 | 軽度の頭痛、倦怠感 |
| 200 ppm | 2〜3時間 | 拍動性頭痛、めまい、吐き気 |
| 400 ppm | 1〜2時間 | 重度の頭痛、意識障害 |
| 800 ppm | 45分以内 | 昏睡、痙攣 |
| 1600 ppm | 20分以内 | 致死的リスク |
病態生理:ミトコンドリアComplex IV阻害
COはヘモグロビン(Hb)と結合するだけでなく、ミトコンドリア電子伝達系のComplex IV(cytochrome c oxidase)に結合し、
ATP産生を阻害 → 細胞レベルの酸素利用を遮断 → 臓器障害を引き起こします。
遅発性神経障害(DNS)にも注意
一度改善しても、数日後に記憶障害・性格変化・錐体路障害などが出現することがあります。
これは「再分布」ではなく、神経の虚血+炎症性脱髄反応と考えられています。
疑ったら即換気・酸素投与・SpCO or ABG確認を!
それでは次に、今回の症例に対して実際にどのような仮説を立て、鑑別を進めていくかを考えてみましょう。
頭痛をどう考える?まずはFact・Problem・Hypothesisで整理しよう
ここまでで、「頭痛=片頭痛」と短絡的に考えず、二次性頭痛を除外する視点が重要だということを確認しました。
それでは、実際の症例をもとに、どのように仮説を立てていくのかを一緒に見ていきましょう。
🩺 医師と患者の会話から
医師:「今日はどうされましたか?」
患者:「ここ2〜3日、左側の頭がズキズキして痛いんです。光が眩しくて、吐き気もあります…。ずっと寝てても良くならなくて…」
🧠 頭の中のつぶやき:
「なるほど、ズキズキとした拍動性、片側性、吐き気と羞明…これは典型的な片頭痛っぽい。
でも、今回の頭痛は“初めて”なのか?それとも“いつもと違う”のか?Red flagを見逃してはいけない場面かもしれない。」
✔ Fact(事実:患者の言葉から)
- 30代女性
- 2〜3日前からの左側性ズキズキ頭痛
- 光が眩しく、吐き気を伴う
- 横になっても改善せず、日常生活に支障がある
✔ Problem(再定義:何が問題か?)
- 拍動性・片側性・羞明・悪心 → 片頭痛様の特徴
- ただし、発症様式(sudden vs gradual)や経過、既往の有無など、Red flagがないとは言い切れない
- 視覚異常、麻痺、発熱などの随伴症状も未確認
✔ Hypothesis(仮説:VITAMIN CDEで思考を広げる)
| 分類 | 疾患候補 |
|---|---|
| Vascular | くも膜下出血、脳静脈洞血栓症、高血圧性脳症 |
| Infection/Inflammation | 髄膜炎、側頭動脈炎(GCA) |
| Trauma | 慢性硬膜下血腫 |
| Autoimmune | CNS血管炎、SLE関連 |
| Neoplastic | 脳腫瘍(朝方・進行性) |
| Congenital | AVM(若年のSAH原因) |
| Degenerative | 緑内障(視野障害・眼痛) |
| Endocrine/Metabolic | CO中毒、PMS、妊娠性片頭痛、低Na、高CO₂ |
📝 NTK(Need To Know)=この後の問診・診察で明らかにすべきポイント
ここでいったん立ち止まり、「この頭痛が片頭痛だと決めつけて良いのか?」という視点で情報を整理しておきましょう。
| カテゴリ | 確認したいこと |
|---|---|
| HPIの詳細 | 今回の頭痛が初発か?過去と違う性質か?突然か、徐々にか? |
| 随伴症状 | 発熱、項部硬直、視覚異常、麻痺、けいれんの有無 |
| 服薬・既往歴 | ピル服用歴、緑内障やSLEなどの疾患 |
| 生活環境 | 冬季、換気不良、家族も頭痛 → CO中毒の疑い |
| 社会的背景 | ストレス、睡眠不足、VDT症候群など |
| 月経周期 | 月経関連性あり? → ホルモン性片頭痛 |
このように、片頭痛らしい症状であっても、Red flagを念頭に置いて慎重に問診・身体所見を進めることが重要です。
それでは次に、OPQRSTとPAM HITS FOSSを用いた問診アプローチを確認していきましょう。
Step 1:問診|頭痛診療に必須の2つのフレーム:OPQRST+PAM HITS FOSS
ここからは症例を一旦離れて、あらゆる頭痛に対応できる問診の型を身につけていきましょう。
特に大切なのは、「痛みの質・発生様式(OPQRST)」に加えて、「背景にあるリスクや病歴(PAM HITS FOSS)」を統合して評価することです。
これにより、Red flagの早期発見と、適切な鑑別診断の整理が可能になります。
🧭 OPQRST:痛みの特徴からヒントを得る
| 項目 | 質問例 | 意義 |
|---|---|---|
| O(Onset) | いつ始まりましたか?突然ですか? | thunderclap headacheならSAH(くも膜下出血)を強く疑う |
| P(Palliative/Provocative) | 何で楽になりますか?何が悪化させますか? | 暗室で楽=片頭痛、前屈で悪化=副鼻腔炎、体動で増悪=SAH |
| Q(Quality) | どんな痛みですか?ズキズキ?締め付けるような? | 質で片頭痛(throbbing)、緊張型(tight)などを推定 |
| R(Radiation) | 首や肩、目の奥などに広がりますか? | 緊張型、群発、髄膜炎などの診断補助 |
| S(Severity) | どのくらい痛いですか?(0〜10)生活に支障は? | 寝込むレベルなら片頭痛や緊急疾患の可能性 |
| T(Timing) | どのくらい続きますか?繰り返しますか? | 片頭痛は4〜72時間、群発は周期性がある |
📋 PAM HITS FOSS:背景要因を網羅的にチェック
| 項目 | 確認すべきポイント | 参考疾患 |
|---|---|---|
| Previous/Past history | 片頭痛・緑内障・SLEなどの既往 | 緑内障、GCA、CNS疾患 |
| Allergy | NSAIDsやトリプタンのアレルギー | 治療制限の把握 |
| Medications | ピル・β遮断薬・抗うつ薬など | 静脈洞血栓症、薬剤誘発性頭痛 |
| Hospitalization | 脳梗塞、外傷歴 | 慢性硬膜下血腫など |
| Injury | 最近の頭部打撲 | 慢性硬膜下血腫 |
| Trauma(精神的) | ストレス、喪失体験 | 緊張型、片頭痛の誘因 |
| Surgery | 頭部・眼科手術歴 | 緑内障、視神経障害 |
| Family history | 片頭痛、脳卒中の家族歴 | 遺伝的素因 |
| OBGYN | 月経周期、妊娠中か | ホルモン性片頭痛 |
| Sexual history | 性感染症の既往 | 髄膜炎、HIV関連疾患 |
| Social history | 喫煙、VDT作業、睡眠、運動 | 緊張型、VDT症候群 |
💡Tips:VDT症候群に関連する頭痛の見極め方
VDT症候群(Visual Display Terminal syndrome)とは、長時間のパソコン・スマホ作業により、目の疲れ・肩こり・頭痛が生じる状態です。
- 英語圏では Digital Eye Strain(DES) や Computer Vision Syndrome(CVS) が一般的な用語。
- 「夕方に悪化」「目の疲れと同時に頭痛」「PC作業後にズーンと痛む」などが特徴。
緊張型頭痛や視覚疲労性頭痛の一因とされ、以下の点を問診で確認しましょう:
- 画面を見る時間(連続使用時間、休憩の有無)
- 姿勢・首肩の緊張・ドライアイの有無
- 眼精疲労や視力変化(眼科受診歴含む)
💡Tips:片頭痛の診断に使える質問紙・スクリーニングツール
片頭痛の診断や重症度評価には、以下のような国際的に使用される質問紙があります:
- ICHD-3(国際頭痛分類)
正式な診断基準(A〜E)で、発作頻度・持続時間・症状の組み合わせで診断。
🔗 https://ichd-3.org/1-migraine/ - ID Migraine™ Screener
3問の簡易スクリーニング(羞明、吐き気、生活への影響)
🔗 PubMed (Lipton 2003) - MIDAS(Migraine Disability Assessment)
頭痛による日常生活への支障をスコア化
🔗 MIDAS PDF - HIT-6(Headache Impact Test)
QoLへの影響を6問で評価。研究や保険対応にも使われる。
🔗 https://www.headachetest.com/
診断の確定だけでなく、治療方針の調整や経過観察にも役立ちます。
このように、症状+背景の評価を丁寧に行うことで、一次性・二次性の判断精度が格段に高まります。
それでは次に、身体診察で“見逃してはいけない所見”をどのように評価するかを見ていきましょう。
Step 2:身体診察|Red Flagを“全身+神経+眼”から見逃さない
問診でRed flagの可能性が浮かんだとき、次に行うべきは、意図を持った身体診察です。
「何となく診る」のではなく、「Red flagの項目を潰していく」という構造的な視点が大切です。
また、頭痛の原因が“内臓”ではなく“筋骨格”にあるケースも多く、POCUSも重要になります。
🔍 全身〜神経所見の系統的な確認ポイント
| 評価項目 | 確認すること | 想起される疾患 |
|---|---|---|
| 意識レベル・姿勢 | 傾眠、姿勢異常、GCS | SAH、髄膜炎、脳腫瘍 |
| 眼球運動・視野・複視 | 斜視、視力低下、眼球運動障害 | 緑内障、腫瘍、脳神経麻痺 |
| 眼底所見(Fundoscopy) | 乳頭浮腫、視神経蒼白、出血 | 頭蓋内圧亢進、視神経炎 |
| 側頭動脈触診 | 硬結、拍動の減弱、圧痛 | GCA(側頭動脈炎) |
| 項部硬直・Kernig/Brudzinski徴候 | 髄膜刺激徴候の有無 | 髄膜炎、SAH |
| 神経学的所見 | 片麻痺、感覚障害、失調、痙攣 | 脳血管障害、CNS感染症 |
| バイタルサイン | 発熱、高血圧+徐脈、頻呼吸 | 感染症、Cushing triad、CO中毒 |
💡Tips:副鼻腔の診察も忘れずに
副鼻腔炎(副鼻腔頭痛)は、特に前頭部・顔面中央の鈍痛として現れることがあり、緊張型頭痛や片頭痛との鑑別が難しいこともあります。
疑うべき症状:
- 前頭部・頬部の圧迫感(重さ)
- 顔面圧痛・副鼻腔の圧痛
- 膿性鼻汁、後鼻漏、咳嗽(特に夜間)
- 上顎歯痛(上顎洞炎による)
診察で行うべき評価:
- 副鼻腔部(前頭洞・上顎洞)の圧痛:眉の上、頬骨下部を優しく圧迫
- 叩打痛(Percussion):副鼻腔の骨を軽く叩いて響く痛みを確認
- 鼻腔内視診(可能であれば):粘膜の腫脹、膿性分泌物を確認
- 眼窩・頬部の発赤・腫脹:蜂窩織炎との鑑別も視野に
慢性副鼻腔炎では、痛みが目立たないこともありますが、「顔の奥が重い」「鼻声が続く」「午後に悪化する」などの訴えがヒントになります。
💡Tips:眼圧測定と耳鏡診察の重要性
👁️ 眼圧測定(Tonometry)
急性閉塞隅角緑内障は視野異常と共に“激しい眼痛+頭痛+嘔吐”を呈することがあり、見逃すと失明リスクがあります。
眼球圧痛がある場合、眼圧が20mmHg以上なら要注意、30mmHg以上は緊急対応の目安。
👂 耳鏡診察(Otoscopy)
中耳炎や乳突蜂巣炎による頭痛は、片側性+発熱+耳の違和感を呈します。鼓膜の発赤・膨隆・滲出液を確認しましょう。
- 中耳炎 → 鼓膜の発赤・膨隆・可動性低下
- 外耳炎 → 外耳道の腫脹、圧痛、耳介牽引痛
- 耳下腺炎や膿瘍 → 耳下部の腫脹、開口時痛
💡Topics:筋緊張型頭痛に関連する筋とトリガーポイント
筋緊張型頭痛(TTH)は、姿勢不良やVDT作業などによって引き起こされる、現代的な頭痛の代表です。
特定の筋に過緊張や圧痛点(トリガーポイント)が生じると、そこから頭部への関連痛が波及し、頭痛として感じられます。
| 筋名 | 放散する痛みの部位 | 診察ポイント |
|---|---|---|
| 僧帽筋(上部) | 後頭部、側頭部、眼窩周囲 | 肩上部、首の付け根 |
| 胸鎖乳突筋(SCM) | 額、側頭部、眼の奥 | 耳の下〜鎖骨内側 |
| 後頭下筋群 | 後頭部、眼の奥 | C1〜C2付近の圧痛 |
| 側頭筋 | 側頭部、こめかみ、上下の歯 | こめかみの圧痛で再現性あり |
| 咬筋 | 顎関節周囲、頬、耳前部 | 下顎角・頬中心部の圧痛 |
再現性のある圧痛=診断のヒント!
「このあたりを押すと、いつもの頭痛が再現されますか?」と聞いてみましょう。
🧱 Column|高血圧性緊急症(Hypertensive Emergency)と頭痛
高血圧性緊急症(hypertensive emergency)とは、著明な血圧上昇に加えて標的臓器障害を伴う状態を指します。
これに対し、高血圧性緊急状態(urgency)は血圧は高いものの、臓器障害を伴わない点が異なります。
- Emergency: BP ≧180/120mmHg + 臓器障害あり
- Urgency: BP ≧180/120mmHg + 臓器障害なし
主な原因疾患:
- 脳出血・脳梗塞・高血圧性脳症
- 急性大動脈解離
- 心不全・肺水腫
- 腎不全・急性糸球体腎炎
- 妊娠中毒症(HELLP症候群、eclampsia)
頭痛と関連が強いパターン:
- 高血圧性脳症:拍動性頭痛、視覚異常、意識障害
- 脳出血:急性の激烈な頭痛、片麻痺、嘔吐
診断のための検査:
- 血圧測定(両側)、尿所見(蛋白・血尿)、眼底所見(出血・浮腫)
- 頭部CT(脳出血・脳浮腫の確認)
- 血液検査:腎機能、電解質、LDH、血小板
注意: 急激な降圧は禁忌となる場合がある(脳虚血悪化)。段階的な降圧を検討すべきです。
それでは次に、仮説と身体所見を踏まえて、必要な検査・画像をどのように選択していくかを考える【Step 3:検査・画像】に進みましょう。
Step 3:検査・画像|目的を明確にして“狙って検査する”
問診と身体診察で仮説が立ったら、次に必要なのは「何を疑って、何を確かめたいのか」という視点を持った検査選択です。
「とりあえずCT」「念のためMRI」ではなく、Red flagがあるのか?臓器障害は?構造異常か?感染か?を明確にして検査に進みましょう。
🔍 主な検査と目的の一覧
| 検査 | 目的 | 疑う疾患 |
|---|---|---|
| 頭部CT(非造影) | 出血・mass lesionの早期評価 | SAH、脳腫瘍、脳出血 |
| 頭部MRI/MRA | 梗塞・構造異常・血管炎 | 静脈洞血栓、CNS vasculitis、腫瘍 |
| 腰椎穿刺(ルンバール) | 髄膜炎・SAHの除外 | 髄膜炎、SAH(CT陰性時) |
| 眼底検査 | ICP上昇・視神経所見 | 乳頭浮腫、視神経炎、HT緊急症 |
| 眼圧測定 | 急性緑内障の確認 | 緑内障性頭痛 |
| 血液検査(CBC, CRP, ESR) | 感染・炎症・血管炎の評価 | 髄膜炎、GCA、腫瘍 |
| PCT(プロカルシトニン) | 細菌感染の指標 | 髄膜炎、脳膿瘍 |
| 側頭動脈エコー | Halo signの確認 | GCA(側頭動脈炎) |
| 副鼻腔CT | 副鼻腔炎の評価 | 急性/慢性副鼻腔炎 |
🧠 つぶやき例(検査選択の思考)
- 「突然の激烈な痛み=まずはCTでSAHを除外しないと」
- 「CTが陰性でもSAHが否定できないなら、ルンバールも必要かも」
- 「高齢でこめかみが痛い…炎症反応+側頭動脈エコーでGCAの判断ができそう」
- 「視野異常や眼の圧痛があれば、眼圧測定と眼科連携を」
- 「明らかな神経所見がなく、鈍い痛みが続く場合は、副鼻腔CTも考えておこう」
⚖ CTとMRIの使い分け(頭痛診療において)
| 比較項目 | CT | MRI |
|---|---|---|
| 撮影時間 | 数分(早い) | 数十分(時間がかかる) |
| 得意な疾患 | 出血、mass lesion | 脳梗塞、小病変、血管炎 |
| 使用場面 | 救急・SAH疑い・意識障害 | 経過観察・診断精度重視 |
| 限界 | 小さな梗塞・髄膜炎・血管病変は見落とす | 撮影できない患者あり(金属、拘束不能など) |
🩺 ルンバール(腰椎穿刺)の適応と注意点
- 適応:
・髄膜炎が疑われる場合
・SAHが疑われるがCTで陰性(特に発症6時間以降) - 注意点:
・頭蓋内圧亢進の所見がある場合(乳頭浮腫など)では禁忌 → まずCTを行う
除外診断の「最後の砦」として、ルンバールは非常に強力な手段になります。
🧪 その他の補助検査
- CRP / PCT: 細菌性 vs ウイルス性の鑑別(高PCT → 細菌性感染)
- ESR: GCAスクリーニング(50mm/h以上で精査を)
- Na: 低Naによる頭痛・意識変容・けいれんの可能性も
- COHb: CO中毒の疑いがあればSpCOまたはABGで確認
このように、検査の選択には仮説 → 検証 → 判断という流れを持つことが重要です。
それでは、検査で二次性を疑う器質的な病変が見つからなかった場合はどう考えましょうか
Step 3.5:一次性頭痛の分類と特徴|Red flagがなければ何を考える?
問診・身体診察・検査を通してRed flagが否定され、二次性頭痛の可能性が低くなった場合、最後に考えるのは一次性頭痛(Primary Headaches)です。
一次性頭痛は、明らかな器質的病変がないにも関わらず、生活の質を大きく損なう疾患群です。
適切に分類・診断し、必要に応じて治療や生活指導を行うことで、患者のQOLを大きく改善することができます。
🔎 一次性頭痛の代表的な3分類
| 分類 | 代表疾患 | 特徴 |
|---|---|---|
| ① 片頭痛(Migraine) | 前兆あり / なし | 拍動性、片側性、羞明・悪心、数時間〜3日、日常生活に支障 |
| ② 緊張型頭痛(Tension-type) | 反復性・持続性 | 両側性、締め付ける痛み、軽〜中等度、筋緊張や姿勢不良に関連 |
| ③ 群発頭痛(Cluster Headache)など TACs: 三叉神経自律神経性頭痛群 |
Cluster, PH, SUNCT, SUNA | 激烈な眼窩痛、涙・鼻漏・眼充血などの自律神経症状を伴う |
🧠 詳細な臨床像と診断のヒント
- 片頭痛: 拍動性、片側性、悪心・光過敏を伴う。動くと悪化し、寝込むことが多い。前兆がある場合は閃輝暗点やしびれが出現。
- 緊張型頭痛: 両側性で「締め付けられる」ような痛み。日常生活は可能だが不快感が続く。精神的ストレスやVDT作業との関連が強い。
- 群発頭痛(Cluster): 男性に多く、激烈な眼窩痛が同時刻に毎日出現。眼充血・涙・鼻水を伴い、数週間続いたのち寛解する。
💡Tips:TACs(Trigeminal Autonomic Cephalalgias)の分類と治療
TACsは激しい頭痛と自律神経症状を特徴とする一次性頭痛群です。
群発頭痛の他にも、稀少疾患としてParoxysmal Hemicrania(PH)やSUNCT/SUNAが含まれます。
| 疾患名 | 持続時間 | 頻度 | 治療 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Cluster Headache | 15〜180分 | 1〜8回/日 | 酸素吸入、トリプタン、Verapamil(予防) | 夜間に多い、発作期あり |
| Paroxysmal Hemicrania(PH) | 2〜30分 | 数回/日 | Indomethacin(診断・治療効果) | Indomethacinが劇的に効くのが特徴 |
| SUNCT | 5〜240秒 | 数十〜数百回/日 | Lamotrigine、Topiramate | 短時間・高頻度の眼痛+結膜充血 |
| SUNA | 数秒〜数分 | やや少なめ | 同上(SUNCTに準ずる) | 涙や鼻漏が伴わないタイプ |
Clinical Pearl: 発作が短く、頻回で眼の充血や涙がある頭痛にはTACsを常に疑いましょう。特にSUNCT/SUNAは見逃されやすく、群発頭痛と混同されやすい点に注意が必要です。
🧪 一次性頭痛と診断された後の対応
- 急性期治療: NSAIDs、トリプタン、酸素吸入(群発)など
- 予防薬: β遮断薬、Topiramate、Verapamil(群発)など
- 生活指導: 睡眠、ストレス、食事(チーズ・赤ワインなどの誘因)
- 頭痛ダイアリー: 頭痛のパターンや誘因を記録することで診断精度・治療効果が向上
このように、一次性頭痛の診断には詳細な問診が欠かせません。そして、分類・特徴を押さえておくことで、治療戦略が大きく変わります。
🧱 Column|チーズや赤ワインで頭痛が起こる理由とは?
患者さんから「ワインを飲むと頭が痛くなる」「チーズを食べたあとに片頭痛が起きた」といった訴えを受けることがあります。
実はこれらの食品にはチラミン(tyramine)という成分が含まれており、片頭痛の誘因となることが知られています。
🔬 チラミンとは?
チラミンはアミノ酸から分解される天然のモノアミンで、熟成食品・発酵食品に多く含まれます。
チラミンには血管収縮作用があり、脳血管が反射的に拡張することによって、拍動性の頭痛を引き起こすことがあります。
| チラミンを多く含む食品 |
|---|
| 赤ワイン、熟成チーズ(ブルーチーズ、パルメザンなど) |
| チョコレート、発酵食品(納豆、味噌、醤油) |
| 加工肉(ハム、サラミ)、酢漬け、熟成魚 |
🧠 頭痛との関連
- チラミンはノルアドレナリンの遊離を刺激し、脳血管に変動を与えることで片頭痛を誘発
- 特に「食後数時間で起こる頭痛」「誘因が一定している」場合は関連を疑う
- 全員に影響が出るわけではなく、感受性の高い患者でのみ誘発される
📌 指導ポイント
- 患者に頭痛日記をつけてもらい、誘因となる食品の傾向を把握
- 明らかな関連がある場合は、その食品を制限または回避するようアドバイス
ちなみに… Parkinson’s disease (PD)や抗うつ薬の一部であるMAO阻害薬(MAOIs)を服用している患者では、このチラミン摂取が命に関わる事態を招くこともあります。
💊 MAOIsとチラミンの関係(チラミン中毒)
MAOIsはモノアミン酸化酵素(MAO)を阻害することで、神経伝達物質(セロトニン、ノルアドレナリンなど)を増やす作用を持ちます。
しかし、同時にチラミンの代謝ができなくなり、体内でチラミンが急激に蓄積します。
その結果…
- ノルアドレナリンが過剰放出され、急激な高血圧(BP > 180/120)
- 拍動性頭痛、視覚異常、発汗、動悸などを呈し、高血圧性脳症や脳出血のリスクも
🔒 MAOIs服用中に禁忌とされる食品
- 熟成チーズ、赤ワイン、納豆、味噌、醤油
- 発酵肉類(サラミ、ハム)、一部のビールや酵母製品
🧠 まとめ:片頭痛とMAOI服用中のチラミン反応の違い
| 項目 | 片頭痛 | MAOIs服用時 |
|---|---|---|
| 誘因 | チラミン含有食品 | チラミン含有食品 |
| 機序 | 血管収縮 → 反射的拡張 → 頭痛 | チラミン代謝不能 → ノルアド過剰 → 高血圧発作 |
| 主な症状 | 拍動性頭痛、羞明、悪心 | 激烈な頭痛、発汗、BP上昇、脳卒中リスク |
| 対応 | 食事制限(必要に応じて) | 厳格な食事制限+服薬指導 |
「ワインやチーズを食べたら頭痛がした」と言われたら、片頭痛か?薬剤との相互作用か?の2方向から考えるのがコツです。
それでは、次に、最初の症例に戻り、ここまでの診断プロセスを実際にどう適用するかを振り返ってみましょう。
症例で振り返る|最初の症例に一つずつ適用してみよう
さて、ここまでStep 1〜3の基本的なアプローチを整理してきました。
では実際に、最初に紹介した症例をもとに、問診・身体診察・検査を一つずつ適用しながら、診断までのプロセスを振り返ってみましょう。
🟦 Step 1:問診の振り返り(Fact → Problem → Hypothesis)
医師:「今日はどうされましたか?」
患者:「ここ2〜3日、左側の頭がズキズキして…光が眩しくて吐き気もして、横になってても辛くて…」
🧠 つぶやき:「典型的な片頭痛っぽいけど、Red flagは本当にないか確認したい。発症様式や随伴症状も丁寧に聞いておこう」
🔎 OPQRST
- O:数日前からじわじわと
- P:暗室で改善、体動で悪化
- Q:拍動性のズキズキ
- R:左側頭部中心、眼の奥まで響く
- S:8/10。寝込むほどの痛み
- T:生理前から。今回が一番ひどい
📋 PAM HITS FOSS
- 過去に軽度の頭痛あり、今回が最重度
- 低用量ピル内服中、母が片頭痛持ち
- デスクワーク8時間/日、寝不足、ストレスあり
🧠 Hypothesis
- 片頭痛(without aura)が最も疑わしい
- ただしSAH、静脈洞血栓、緑内障、GCAなども念のため除外
📋 ID Migraine™ Screenerを使ってみると?
以下の3つの質問のうち、2つ以上が“Yes”であれば、片頭痛の可能性が高い(感度81%、特異度75%)。
- 光に敏感になりますか? → Yes
- 頭痛時に吐き気や嘔吐がありますか? → Yes
- 頭痛で生活や活動に支障がありますか? → Yes
→ 3/3が“Yes”。ID Migraineスクリーナー陽性 → 片頭痛の可能性高いと判断できる。
🟦 Step 2:身体診察の振り返り
意識清明、GCS 15、神経学的所見なし。項部硬直・視力異常・眼球圧痛・乳頭浮腫なし。
側頭動脈も正常でGCAの所見なし。
→ Red flagを否定できた。
🟦 Step 3:検査・画像の振り返り
- 頭部CT:明らかな出血やmass lesionなし
- 眼圧:正常(18 mmHg)
- 血液検査:CRP・PCT・ESRすべて正常
→ 検査でもRed flagの根拠は見つからず、一次性頭痛と診断してよい状況。
🧭 それでは次に…
この症例は、重篤な二次性頭痛の可能性が否定され、一次性頭痛(片頭痛)と診断されました。
それでは次に、片頭痛に対して非専門医や家庭医ができる初期対応・生活指導について確認しておきましょう。
片頭痛に対する非専門医の実践的対応と生活指導
片頭痛(migraine)は、患者のQOLに大きな影響を与える一方で、非専門医でも十分に初期対応・マネジメントが可能な疾患です。
特にAura(前兆)の有無による分類は、診断や治療、将来的なリスク評価に影響を及ぼすため、正しく理解しておく必要があります。
🧠 片頭痛の2つのタイプ:with aura と without aura
ICHD-3では片頭痛を以下の2つに分類しています:
- 1.1 Migraine without aura: 前兆のない片頭痛。最も一般的なタイプ。
- 1.2 Migraine with aura: 視覚・感覚・言語などの前兆を伴うタイプ。
この分類は単なる症状の違いではなく、発症メカニズム・脳血管イベントのリスク・治療選択にも影響する重要な視点です。
🔬 なぜ区別するのか?
- with aura: 皮質拡延性抑制(Cortical Spreading Depression)という神経活動の波が関与。
- without aura: 三叉神経系の活性化、血管周囲の炎症性ペプチド放出などが主な機序。
- with auraは脳梗塞のリスクがやや高いとされ、ピルの使用など慎重な判断が必要。
🔄 移行はあるのか?
片頭痛はライフステージやホルモン変動、生活習慣の変化によって、with aura ⇄ without auraを行き来することがあります。したがって、一度の分類に固執せず、症状が変化した際には改めて評価することが大切です。
🏥 急性期の治療(Acute Therapy)
- 軽度〜中等度: NSAIDs(ロキソプロフェン、アセトアミノフェン)
- 中等度〜重度: トリプタン製剤(スマトリプタン、ゾルミトリプタンなど)
- 悪心や嘔吐を伴う場合: 制吐薬(メトクロプラミド、ドンペリドン)を併用
🔸 トリプタンは月10日以上使用すると「薬物乱用頭痛(MOH)」の原因になる可能性があります。
🛡 予防療法(Prophylaxis)
以下のような患者では、予防薬の導入を検討します:
- 月に4回以上の片頭痛発作
- 急性期治療が効かない、または副作用が強い
- 日常生活に著しい支障がある
代表的な予防薬:
- β遮断薬(プロプラノロール)
- 抗てんかん薬(バルプロ酸、トピラマート)
- Ca拮抗薬(ロメリジン)
- 抗うつ薬(三環系など)
※ CGRP関連抗体(エムガルティなど)は高頻度例に使用可(保険条件あり)。
📖 生活指導とセルフケア
📌 片頭痛の誘因(Triggers)
- 睡眠不足・過眠
- 脱水、空腹、過労
- ホルモン変動(排卵、生理)
- ストレス、天候・気圧の変化
- 特定の食品(赤ワイン、チーズ、チョコレート)
📝 実践的な指導
- 片頭痛日記の活用
- 水分摂取(1日2L以上)
- 規則正しい睡眠と食事
- ストレッチや眼精疲労ケア(VDT症候群対策)
💬 患者に伝えたいこと
- 「片頭痛はコントロールできる病気」である
- 治療と生活習慣の両輪で予防が可能
- Red flag(麻痺、発熱、突然の激痛など)は速やかに受診を
🧭 次に考えるべきことは?
ここまで、片頭痛を中心とした一次性頭痛に対して、非専門医が実施できる診断・治療・生活指導を確認してきました。
しかし、すべての頭痛がプライマリケアで完結するわけではありません。
重症例や非定型例、治療抵抗性の片頭痛では、専門医の評価や治療が必要になるケースも少なくありません。
それでは次に、どのようなタイミングで専門医へ紹介すべきか、紹介時に準備しておくべき情報や検査結果について確認していきましょう。
12. 専門医に紹介するとき
頭痛は大半が一次性であり、プライマリケアで対応可能ですが、いくつかの場面では専門医の介入が必要です。
特に、Red flagを伴う頭痛・治療抵抗性・二次性頭痛の疑いが残るケースでは、専門的な評価や治療方針の検討が求められます。
🔻 紹介を検討すべき状況
- Red flag症状がある(突然の激烈な痛み、発熱、麻痺、視力低下など)
- 治療に反応しない片頭痛(急性期治療・予防療法ともに不十分)
- 月に15日以上の慢性頭痛や、薬物乱用頭痛(MOH)が疑われる場合
- 構造的病変(腫瘍、脳血管疾患など)の可能性がある場合
- 神経学的異常を伴う新規の頭痛(視野欠損、失語、運動障害など)
- 脳脊髄液減少症(起立時頭痛)の疑い
- 患者の不安が強く希望がある場合
📋 専門医紹介前に確認しておきたい検査・情報
専門医にスムーズに引き継ぐためには、以下の情報を整理しておくと有用です。
- 問診情報: 頭痛の発症様式・頻度・持続時間・誘因・随伴症状(OPQRST)
- 既往歴・内服歴: 抗凝固薬、ピルなどは特に重要
- 神経学的身体診察: 麻痺・失調・感覚異常・視神経乳頭浮腫などの有無
- 頭部画像: CT/MRI(施行済であれば所見付きで添付)
- 血液検査: 炎症反応(CRP, ESR)、電解質異常の有無
- ID migraineスクリーナーや片頭痛日記の記録
🧠 Tips:特に専門医に紹介する前にやっておくと良いこと
- 眼圧・耳鏡検査: 緑内障・中耳炎のスクリーニング
- 頸部の圧痛評価: 筋筋膜性の要素がないかチェック
- 副鼻腔叩打痛: 副鼻腔炎との鑑別
- 患者教育: 頭痛の良性度、予防や生活習慣の重要性について伝える
これらの情報を網羅しておくことで、紹介先の専門医はより的確な判断ができ、患者の不安軽減にもつながります。
🪶 では、日々の診療でどう活かすか?
ここまで、頭痛に対する系統的なアプローチと専門医への紹介基準を整理してきました。
しかし、実際の診療現場では「問診の切り出し方」や「診察時のちょっとしたコツ」が診断の成否を分けることも少なくありません。
それでは次に、頭痛診療で押さえておきたい診察のコツ・現場で使える小技を、いくつか紹介していきましょう。
Clinical Tips & Pearls
🩺 Clinical Tips|問診・診察で役立つコツ
- 「いつから/どう始まったか」を最初に聞くことで、red flag(くも膜下出血など)の早期拾い上げが可能に。
- 「これまでと同じ頭痛ですか?」という質問は、二次性頭痛の除外に非常に有効。
- 眼圧・耳鏡検査・副鼻腔叩打痛を忘れずに。緑内障や副鼻腔炎などの見落としを防ぐ。
- 頭痛の部位を聞く際は前額部/側頭部/後頭部/眼窩部/項部などに分類して具体化を。
- 患者が言葉にしづらい場合は「チカチカする光?」「視野が欠ける感じ?」と例を示すと有用。
- トリガーポイントの圧痛(僧帽筋・後頭下筋群)評価は筋緊張型頭痛に有効。
- VDT(Visual Display Terminal)症候群を疑うときは、眼精疲労・姿勢・休憩習慣も確認。
- 頭痛日記の記録内容を患者と共有すると、予防とセルフケア意識が向上する。
💬 Clinical Pearls
“Beware of the worst headache of one’s life.”
— Emergency Medicine Proverb
(人生で最悪の頭痛には、常に警戒を)
“If a patient says it’s different, believe them.”
— Neurology Teaching
(「これまでと違う」と言う患者の言葉は、信じるべきだ)
“Not all thunderclaps are bleeds, but all bleeds can thunder.”
— Stroke Teaching Pearl
(すべての雷鳴頭痛が出血ではないが、出血は雷のように始まることがある)
Medical English:頭痛診療の英語表現と注意点
🗣 導入:OSCE・国際診療に備える
頭痛診療を英語で行う場面では、問診・診察に使える定型表現に加えて、患者に伝わるわかりやすい言い換え、誤解されやすい表現の回避が不可欠です。
ここでは、資料をもとに臨床現場で活用できる英語表現を7つの観点から整理しました。
💬 Useful Medical Expressions|問診・診察で使える定型表現
- “Can you describe your headache?”
- “Is it sharp, dull, pounding, or pulsating?”
- “How long does it last?” / “How often do you get them?”
- “What triggers the headache?”
- “Do you notice any visual changes?”
- “Do you get warning signs before the headache?”
- “Do you have nausea, fever, or stiff neck?”
🧠 Pain Descriptions|痛みの性質・部位の表現
- Pounding / Banging: ガンガンする
- Throbbing / Pulsating: ズキズキする
- Stabbing / Pricking / Sharp: チクチク、刺すような
- Aching / Dull: 鈍い、シクシク
- Radiating / Tingling: ジーンと広がる感覚
- Squeezing / Pressing / Tight: 締め付けられる感じ
- Pressure-like: 押されるような圧迫感
- Electric / Shooting: ピリピリ、電撃のような
- Burning: 焼けるような
患者に質問する際は:
“Would you say it’s pounding, sharp, or like pressure?” と選択肢を提示するのが有効です。
🌈 Aura & Sensory Changes|視覚異常や前兆の表現
- Flashing lights / Flickering: チカチカする
- Zigzag lines / Fortification pattern: ギザギザの光、城壁模様
- Blurry vision: ぼやける
- Dim / Cloudy vision: かすんで見える
- Numbness / Tingling: しびれ感
- Lightheaded / Woozy: フワフワする、クラッとする
🧑⚕️ Layman’s Terms & Idioms|患者向けの言い換え
- “Migraine” → “A strong headache on one side, with light or sound sensitivity”
- “Tension-type headache” → “A tight band-like pain around your head”
- “Cluster headache” → “Very strong pain around the eye that comes suddenly”
- “Photophobia” → “Does light bother you when you have a headache?”
- “Aura” → “Do you see any flickering lights or strange patterns before the headache?”
- “Nuchal rigidity” → “Is your neck very stiff?”
📘 Medical English Glossary|用語解説
- Migraine: Unilateral, pulsating headache with possible nausea, photophobia, and aura.
- Aura: Neurological symptom before migraine (visual, sensory, speech).
- Photophobia: Light sensitivity, often seen in migraine and meningitis.
- Scotoma: A blurry or blind spot in the visual field.
- Thunderclap headache: Sudden, severe headache peaking within 1 minute. Requires urgent evaluation.
- Triptans: Serotonin receptor agonists for aborting migraine attacks.
- CGRP inhibitors: Medications for migraine prevention targeting calcitonin gene-related peptide.
- Sinus tenderness: Local pain on sinus percussion (suggests sinusitis).
- MOH (Medication Overuse Headache): Headache due to overuse of analgesics.
⚠️ Pronunciation & Usage Pitfalls|間違えやすい発音・誤用
- Migraine: /ˈmaɪɡreɪn/(×「ミグレイン」)
- Aura: /ˈɔːrə/(×「アウラ」)
- Sinus: /ˈsaɪnəs/(×「シナス」)
- Nuchal: /ˈnjuːkəl/ または /ˈnuːkəl/(発音揺れあり)
- Photophobia: /ˌfoʊtəˈfoʊbiə/(×「フォトフォビア」)
- VDT: 日本で用いられるが、英語圏では「Digital Eye Strain / Computer Vision Syndrome」
- “CT was normal”: → より丁寧には “There were no abnormalities on the CT scan.”
🧭 ここまでの内容をふりかえって
ここまで、頭痛の診察に必要なアプローチ、注意すべき疾患、英語での表現方法までを幅広く見てきました。
では最後に、本記事のポイントを簡潔にまとめ、日々の診療にどう活かしていくかを振り返ってみましょう。
記事のまとめ
頭痛という症候は、よくある一方で、命に関わる疾患の入り口でもあります。
だからこそ、単なる「頭が痛い」という訴えの裏にある病態を、冷静かつ体系的に評価していくことが大切です。
本記事では、一次性頭痛と二次性頭痛の鑑別を軸に、問診・身体診察・検査の優先順位を整理し、片頭痛や群発頭痛といった疾患ごとの特徴も確認しました。
また、OSCEや国際診療に備えて、英語での問診・説明に役立つ表現もまとめました。英語での診察では、専門的な言葉よりも、「伝わる表現」が何より大切です。
もし次に「頭痛の患者さん」が来院したら、この記事で得た知識と視点をもとに、少しだけ落ち着いて、深く、問診してみてください。
きっと、いつもと違う何かに気づけるはずです。
そして何より、あなた自身も無理せず、頭痛が続くときは医療者としての自分を守ることも忘れずに。
Let the symptom speak — 頭痛にも、語らせてみましょう。
他の記事も読んでみませんか?
本サイトでは、他にも症候別の診察アプローチ記事を多数掲載しています。
頭痛と関連の深い以下の症候も、あわせてチェックしてみてください。
▼ 英語で同じ内容を学びたい方はこちら:
▶︎ Symptom-Based Approach to Headache [English version]
References
- 日本頭痛学会. 『頭痛の診療ガイドライン2021』. 医学書院.
- 石上友章 他. 『内科診断学 第3版』. 医学書院.
- Ropper AH, Samuels MA, Klein JP. *Adams and Victor’s Principles of Neurology, 11e.* McGraw-Hill Education, 2019.
- Dodick DW. Migraine. *Lancet*. 2018 Jan 6;391(10127):131–144.
- Institute for Healthcare Communication. *English for Medical Professionals: Symptom-based Expressions*. 2020.