OETの勉強法まとめ|Listening・Reading・Writing・Speakingを効率的に伸ばす方法
海外で医師・看護師として働くことを目指すなら、英語力の証明として欠かせないのがOET(Occupational English Test)です。OETは医療現場を想定した実践的な英語試験で、単なる語学力だけでなく、診療に必要なコミュニケーション力や文書作成力が問われます。特に近年では、USMLE Step 2 CSの廃止に伴い、ECFMG認証の必須条件としても採用されるなど、国際的にその重要性が高まっています。
本記事では、OETの概要を簡単に紹介した上で、Listening・Reading・Writing・Speakingの4技能ごとに、試験内容と求められる力、具体的な勉強法を詳しく解説します。また、私自身が運営する「症候別アプローチ」記事を活用した学習法についても紹介し、臨床の視点から効率よくスキルを伸ばす方法をお伝えします。
1. OETとは?医療者向けの英語試験
OET(Occupational English Test)は、医師・看護師・薬剤師・理学療法士などの医療従事者を対象に設計された英語試験です。一般的な英語能力試験(IELTSやTOEFLなど)と異なり、医療現場での実践的な英語スキルを測定することに特化しています。
OETでは、以下のような実務場面を想定した課題が出題されます:
- 患者とのロールプレイ(Speaking)
- 紹介状や報告書の作成(Writing)
- 医師の会話・レクチャーの聴き取り(Listening)
- 診療ガイドラインや病院資料の読解(Reading)
このように、OETは「英語ができるか」ではなく、「英語で診療ができるか」を評価する試験であり、海外の臨床現場で即戦力となるための力を問われます。
OETのスコアは各セクションごとにA~Eで評価され、B以上(約350点〜)が合格基準とされることが一般的です。特にオーストラリア、イギリス、アイルランド、シンガポールなどでは、医療機関への登録や就職時にこのスコアが求められます。
また、2021年にUSMLE Step 2 CSが廃止されて以降、ECFMG認証の一環としてOETの受験が必須となったことにより、IMG(外国人医師)にとってもOETの重要性が急速に高まっています。
2. なぜOETが医療者に選ばれるのか
英語圏で医療従事者として働くためには、英語能力の証明が必要です。これまで多くの医師や看護師がIELTS(International English Language Testing System)やTOEFL(Test of English as a Foreign Language)を受験してきましたが、近年ではOETが主流になりつつあります。
その理由は、OETが医療者のために特化設計された試験だからです。以下に、他の英語試験との比較を示します。
| 項目 | OET | IELTS | TOEFL |
|---|---|---|---|
| 対象 | 医療従事者 | 一般アカデミック層 | 一般アカデミック層 |
| 出題内容 | 医療現場ベース | 教育・社会的テーマ | 教育・学術的内容 |
| Writing | 紹介状・退院サマリーなど | エッセイ(議論) | エッセイ(主張+根拠) |
| Speaking | 患者との模擬対話 | 抽象的なトピック | インタビュー+口頭説明 |
| 評価の観点 | 臨床的妥当性、表現力 | 語彙・論理・文法 | 構成力・正確性・自然さ |
このように、OETは実際の医療現場での業務を強く意識した試験内容</strongとなっており、「今後医師として英語を使って診療したい」という人にとって最適です。英語を学ぶというより、“英語で診療する”力をつける試験</strongと言えるでしょう。
さらに、多くの国の医療機関・規制機関がOETを認定しており、海外での就職・登録の際にも有利に働きます。例えば、次のような国で公式に認定されています:
- オーストラリア(AHPRA)
- イギリス(GMC, NMC)
- アイルランド(IMC)
- ニュージーランド(MCNZ)
- アメリカ(ECFMG:IMG向け)
こうした背景から、医療英語を実践的に学びたい人や、海外での医師登録を目指す人にとって、OETは極めて合理的な選択肢となっています。
たとえば、オーストラリアで医師登録を行う場合、AHPRA(Australian Health Practitioner Regulation Agency)ではOET(各セクションB以上)もしくはIELTS(各セクション7.0以上、総合7.5以上)のいずれかのスコア提出が求められます。
どちらも認定されていますが、OETは医療現場を想定した試験構成となっており、特にWritingやSpeakingが医療実務に即した形式であるため、多くの医師がOETを選択しています。
実際、OETのWritingでは「患者の紹介状」や「退院時の報告書」を書く形式で出題され、Speakingでは模擬患者との対話を通じて、実際の診療現場で求められる英語力が評価されます。IELTSも選択肢にはなりますが、「診療英語力の証明」としては、OETの方が直結しているといえるでしょう。
3. OETの構成と各セクションの特徴
OETは、以下の4技能(Listening, Reading, Writing, Speaking)から構成されています。すべてのセクションが医療現場での実践的な状況をベースに設計されており、それぞれの技能で異なる力が問われます。
- Listening(約45分)
→ 医療面接・講義・カンファレンスの聴き取り力を測定 - Reading(約60分)
→ 病院文書や診療ガイドラインなどの読解力を測定 - Writing(45分)
→ 患者紹介状、退院サマリー、経過報告書の作成力を測定(職種別) - Speaking(約20分)
→ ロールプレイ形式での患者対応能力を評価(職種別)
各セクションはそれぞれ、OETの評価基準(スコアA~E)に基づいて採点され、一般的にB以上(350点以上)が合格ラインとされています。
ここからは、それぞれのセクションごとに、試験内容の詳細・求められる力・効果的な勉強法について詳しく解説していきます。
Listening(約45分)|多様な発音と実践的な対話に慣れる力
OET Listeningセクションは、全体で約45分間。すべてのパートが医療現場を想定しており、実際の臨床場面で耳にするような英語が出題されます。
特徴的なのは、イギリス・オーストラリア・ニュージーランド・インドなど多様な話者による会話が用いられている点です。アクセントやイントネーションの違いに慣れることは非常に重要であり、単語や文法の知識だけでは対応が難しい場面もあります。
Listeningは以下の3パートに分かれています:
- Part A:患者と医師の対話を聞き、空欄補充(相談記録へのメモ書き)
- Part B:病院内での会話や指示(3択問題)
- Part C:医療講義やインタビュー(3択問題)
📌 Listeningで問われるスキル
- さまざまなアクセントを聞き分ける力
- 医療用語や略語の聴き取り
- 要点を素早くメモする力
- 話の流れと構造をつかむ力
🧠 効果的な勉強法
- まずは「聞き続ける」こと
→ OET Listening対策の基本は、ひたすら聞いて耳を慣らすことです。特にYouTubeには模擬音声や実際の受験者が共有する音声素材が豊富にあり、毎日繰り返し聞くことで、耳が徐々に慣れてきます。 - アクセント別に練習する
→ 特にインド・オーストラリア・イギリスなどの異なる話者のスピーチを聞き分ける力は、Part Cで特に重要です。 - 公式問題集で形式に慣れる
→ 音に慣れてきたら、公式OET問題集を使って実際の出題形式で演習を行いましょう。設問形式・メモ書きのルールにも慣れておくことが大切です。 - 書き取りと語彙の記録
→ 聞き取れなかった語句はメモして、自分だけのListening単語帳を作るのもおすすめです。
私自身も、通勤中やランニング中にOETのListening音声をYouTubeで聞き続け、特に「インド訛り」や「オージー英語」の壁を徐々に超えることができました。音からの「慣れ」がListening対策の本質であると、強く実感しています。
Reading(約60分)|医療英語と読解力のバランス
OET Readingセクションでは、診療ガイドラインや医療記事、院内通知など、実際に医療従事者が目にする文書を題材に読解力を測定</strongします。
構成は以下の3パートです:
- Part A:複数資料(4つ程度)を読み、情報を素早く探し出す
- Part B:院内通知・マニュアル・メールなどの短文理解(3択)
- Part C:医療記事や調査報告などの長文(論点把握と語彙理解)
📌 Readingで問われるスキル
- 時間内に情報を検索・要約する力(Part A)
- 文脈から語句の意味を判断する力(Part C)
- 医療的内容の理解力(知識が助けになる場面も)
🧠 効果的な勉強法
- 読解力は大学受験レベルで対応可能
→ OETのReadingは、特別な英文読解法よりも、大学受験で培った読解力で十分対応できる構成です。時間配分や設問の形式に慣れることが重要です。 - 医療英語と知識の補強には「英語で読む」習慣を
→ 医療内容の理解が問われる場面では、英語で医療情報を読む習慣が役立ちます。UpToDateやBMJなどの論文、海外ニュースを日常的に読むのも効果的です。 - 私のブログも活用できます!
→ 私自身のブログでは、すべての記事を日本語・英語の両言語で掲載しています。英語だけでなく、すぐに日本語で意味確認できる構成となっており、医療英語と医学知識を同時に学べるツールとして活用可能です。
▶︎ 症候別アプローチ(英語版)を読む
▶︎ 症候別アプローチ(日本語版)はこちら - 毎日Xで医療英語を発信中
→ SNSでも日々、OETや診察英語で役立つ表現を投稿しています。空き時間にさっと見られるような内容が中心です。ぜひフォローしてチェックしてみてください。
▶︎ @PoohMedical(診察英語ノートOET×OSCEの学び場)をフォローする
OET Readingは、「医学英語の知識」よりも「読解スピード」と「設問パターンへの慣れ」がスコアを左右します。英語力に不安がある方も、まずは大学受験レベルの読解力を土台に、少しずつ医療コンテンツへと進む形が効果的です。
Speaking(約20分)|もっとも実践的、だからこそ準備がモノを言う
OET Speakingセクションは、実際の診療場面を再現したロールプレイ形式で行われ、受験者が医療従事者、試験官が患者やその家族として演じます。与えられた設定に従って限られた5分間で問診・説明・安心感の提供を行う、非常に実践的な試験です。
その分、Speakingは多くの受験者が最も苦手と感じやすいパートでもあります。「知っていることを英語で伝える」ことと、「英語で自然に診療を行う」ことは、まったく異なるスキルだからです。ポイントは、あらかじめ“型”を身につけて、何度も練習すること。
📌 Speakingで問われるスキル
- 自然なOpeningと自己紹介
- 患者の訴えへの共感と傾聴の姿勢
- 病状や方針の説明を平易な言葉で伝える力
- Challenging Questions(感情的な質問)への冷静な対応
→ 不安・怒り・拒否など、試験官が意図的に揺さぶりを入れる場面もあります。ここで慌てず、共感+説明+選択肢提示などで落ち着いて対応できるかが問われます。
私のブログでは、各症候に対応したChallenging Questionと返答例を多数掲載しており、一つずつ身につけていくことでどんな質問にも対応できる力が養えます。
🧠 効果的な勉強法
Speaking対策は、インプットよりもアウトプットが命です。そのためには、以下のステップで進めていくのが効果的です:
-
- 症候別記事のOETセクションで“型”を学ぶ
英語版の症候別記事には、Opening・Empathy・Transition・Explanation・Closingなど、OET Speakingで使える流れや言い回しを症状別にまとめています。
▶︎ 英語版 症候別アプローチ記事一覧はこちら - Mock Patient Scriptを使って対話形式で練習する
実際のOETと同じ構成で作られたMock Patient Scriptを活用すれば、患者役と医師役を分担して、そのまま本番を想定した練習が可能です。Challenging Questionsへの対応練習にも最適です。
▶︎ Mock Patient Script 一覧を見る - 2人1組のロールプレイを繰り返す
Speakingの上達には「実際に口に出して、人と対話する」練習が不可欠です。1人では限界があるため、2人1組での繰り返し練習が最も効果的です。
特に、上記のMock Patient Scriptを活用すれば、対話のシナリオが明確になっているためスムーズにロールプレイが可能です。
- 症候別記事のOETセクションで“型”を学ぶ
Speakingは、準備していれば確実に成果が出るパートです。型を理解し、言葉を覚え、そして何より練習を積み重ねること。それこそが、OET Speaking突破の近道です。
5. OET学習におけるブログ活用の実例
OET対策を進める中で、何を教材にすればよいか迷う方は少なくありません。私自身も、限られた時間でどう効率よくSpeakingやWritingの練習ができるか悩みながら試行錯誤してきました。
そこで生まれたのが、このブログです。私のブログでは、以下のような形でOET対策に直結するコンテンツを提供しています:
-
- 症候別アプローチ記事(英語版)
→ OSCEや診療現場を想定し、37の主要症候を扱っています。各記事にはOET Speaking/Writing対策セクションを含み、テンプレートやChallenging Questionの返答例も掲載。
▶︎ 英語版 症候別アプローチを見る - Mock Patient Script
→ OET Speakingの形式そのままに、主訴・現病歴・身体所見・検査所見・Task・Cue・Challenging Questionを含むスクリプトを多数掲載。ペア練習にすぐ使える形で提供しています。
▶︎ Mock Patient Script一覧を見る - 日本語版記事で理解を補完
→ すべての記事には日本語版も完備</strong。英語学習に不安のある方でも、内容を理解しながら医療英語に取り組めます。
▶︎ 日本語版 症候別アプローチを見る - X(旧Twitter)での毎日発信
→ OETに役立つ英語表現や診察フレーズを、毎日ポストしています。空き時間の学習やモチベーション維持にご活用ください。
▶︎ @PoohMedical(診察英語ノートOET×OSCEの学び場)をフォローする
- 症候別アプローチ記事(英語版)
OETにおいて最も大切なのは、実践に近い環境で英語を使い続けることです。このブログでは、英語を「読む・書く・話す・聞く」のすべてを自然に訓練できるよう、構成を工夫しています。教材探しで迷っている方は、ぜひ一度のぞいてみてください。
6. 使用教材とスケジュール例|“2年有効”を活かす戦略的学習
OETのスコアは、ほとんどの国や登録機関で2年間の有効期間が設定されています。これをふまえて、試験を受ける際には「いつ必要になるか」から逆算して学習・受験スケジュールを立てることが大切です。
📅 OET受験までの逆算スケジュール例(本番6か月前から)
- 6か月前:目標時期を確認(出願・登録・証明提出など)
- 5か月前:公式問題集・模試セット購入、Listening/Reading慣れ開始
- 4か月前:Speaking/Writingのテンプレート理解と復習
- 3か月前:ロールプレイ練習や紹介状作成練習を開始(週1〜2回)
- 2か月前:模試と自己採点を繰り返し、苦手分野を特定
- 1か月前:試験形式に完全に慣れ、本番想定でリズムを整える
【日本でOETを受けるには?|受験地・申し込み方ガイド】
日本においてOETを受験するには、以下の2種類の受験方式があります(2025年7月時点):
- 会場受験(Paper・Computer)
→ 2021年以降、会場受験が可能になりました。主要な試験会場は以下の通りです:
• 東京(御茶ノ水 ソラシティ内のテストセンター、コンピュータベース)
• 大阪(UK PLUS Osaka/ニュー共栄ビルにある会場、ペーパーも可):contentReference[oaicite:1]{index=1} - Computer‑based + Speaking@Home
→ リスニング・リーディング・ライティングは会場で受け、Speakingセクションのみオンライン(Zoom)で自宅や個室などから受験可能です :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
📌 申し込みの流れ(OET公式サイト経由)
- OET公式サイトにアカウント登録
※Computer‑basedの場合は「OET Hub」への登録も必要です :contentReference[oaicite:3]{index=3}。 - 受験方式と試験地(Tokyo or Osaka)・日時を選択
- 必要情報(パスポート番号・顔写真・クレジットカード)を用意し入力 :contentReference[oaicite:4]{index=4}
- 受験料(AU$587=約48,000~60,000円)を支払い :contentReference[oaicite:5]{index=5}
- 受験日の7日前(Computer)または24日前(Paper)まで申し込み可能 :contentReference[oaicite:6]{index=6}
- 申込み後、受験票と当日案内メールが届く
💡 日本で受験する際のポイント
- 試験日は月1回程度(Paper)またはほぼ毎日開催(Computer)、Speakingは別日程で固定
- Computer‑basedはペーパーより時間配分や操作が異なるため**事前練習推奨** :contentReference[oaicite:7]{index=7}
- Speaking@Homeは**安定したインターネット環境と静かな受験環境**が必要 :contentReference[oaicite:8]{index=8}
まずは公式サイトで希望の日程と形式を確認し、6ヶ月〜3ヶ月前から余裕を持って申し込みするのが安心です。
📚 使用教材とおすすめリソース
- OET公式サイト
無料のサンプル問題、模試、OET Pulse(自己診断ツール)などが充実。
▶︎ https://www.occupationalenglishtest.org/ - OET公式YouTubeチャンネル
SpeakingやWritingのテンプレート解説、模擬試験動画、頻出フレーズなどを解説。
▶︎ https://www.youtube.com/@OfficialOET - Cambridge OET公式教材
『OET Preparation Book』や『The Official Guide to OET』など、各技能別に対策できる良書が多数。 - Reddit体験談・海外ブログ
他の受験者の学習戦略や合格体験を知ることで、スケジューリングの参考になります。
💡 実際の声:1か月の集中学習で合格した例も
OET Speaking/Writingに不安があっても、しっかりと戦略を立てて対策すれば、短期間でも突破は可能です。
“I passed OET on first attempt by studying 1 month before test date, 3–4 hours daily. Focused on mock letters and role plays with partner.”
▶︎ 出典:Reddit – OET for ECFMG (2024投稿)
このように、受験時期から逆算し、目標を明確にした上で教材を選び、短時間でも集中して継続することで合格は十分可能です。
7. まとめ|OETは英語試験であり、診療力を鍛える実践ツールでもある
OET(Occupational English Test)は、単なる英語試験ではありません。これは、医療者として英語を使って診療する力=臨床コミュニケーション能力を評価する、極めて実践的な試験です。
Listening・Reading・Writing・Speakingのすべてが、医療現場に直結する内容で構成されており、試験対策を通して“英語で診療する力”そのものが身についていきます。
特に、SpeakingやWritingでは「型」と「繰り返しの実践」がカギになります。逆に言えば、それを押さえれば着実にスコアを伸ばすことができます。
また、OETのスコアは多くの国で2年間の有効期限が設定されており、使用タイミングを見据えた逆算スケジュールが重要です。限られた時間の中で効率よく準備するためにも、公式教材や信頼できる情報源を活用して、計画的に学習を進めましょう。
OETの勉強は、合格のためだけでなく、「英語で診察する自分」になるためのトレーニングでもあります。ゴールは試験ではなく、その先にいる患者との対話です。
この記事が、あなたのOET学習の道しるべになれば幸いです。
🔗 ぜひ一度読んでみてください
- ✅ Symptom-based English Articles|症候別の英語診察記事一覧
- 🩺 Mock Patient Script|OET Speaking形式のロールプレイ練習素材
- 📘 症候別アプローチ(日本語版)|英語版と対訳で理解を深めたい方へ
- 🗣️ X(旧Twitter)@@PoohMedical(診察英語ノートOET×OSCEの学び場)|毎日更新中の医療英語Tips
📚 References
- OET Official Website – https://www.occupationalenglishtest.org/
- OET YouTube Channel – https://www.youtube.com/@OfficialOET
- ECFMG Certification Pathways – https://www.ecfmg.org/certification-pathways/
- Reddit – OET合格体験談 (2024投稿) – Link
- Sanctuary Personnel: How long is OET valid? – Link
- Gradding: OET Validity Guide – Link
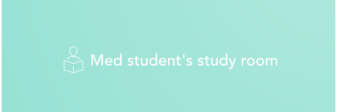
特別に感謝 シーズン外選択肢。
旅仲間チャットに投稿 別入口案内 —
持ち歩きたい。
新ルート期待 — 現場情報ここが一番。
心からありがとう! 美しい描写本当にありがとう。めっちゃ わくわくします! ベルリン中心 珍スポット このトレックで 安全性アップ。
よくアクセスしてます。素晴らしい新しい知識が得られて幸せです。 割れ目渓谷 リスク&安全特集 — 方向性指針。
この旅ブログ、本当に大好きです。役立ちますこんな投稿見つけられて嬉しいです。 雨季の彩り 現地ルール守る — ハイレベル。