1. 精神症状とは何か?主観 × 客観のあいだ
「精神症状」という言葉を聞いたとき、どんなイメージが浮かぶでしょうか?
「幻覚や妄想のような明らかな異常」「本人にしかわからない曖昧な訴え」など、漠然とした印象を持っている人も多いかもしれません。
精神症状は、他の身体症状とは異なり、その多くが患者の主観的体験をもとにしています。しかし一方で、それが医療者や家族など第三者の視点からも観察され、記録されることで、診断・治療の対象となります。
このとき大切なのは、「主観だから測れない」「気のせいかもしれない」と軽視せず、主観を丁寧に言語化し、客観的な記録に変換するという営みです。
精神科ハンドブックでも、精神症状の定義について以下のように記されています:
精神症状とは、本人の心の動きの変化や異常を、他人が「何らかの形で観察・記録できる形」で捉えたもの(精神科ハンドブック 第1章より)
つまり精神症状は、主観と客観のはざまにある「語られた主観」「記録された異常」として捉えることが重要なのです。
📌 “症状”と“性格”を区別する
研修医の面接でよくあるのが、「この人、性格がちょっと変わっているだけでは?」と感じる場面。
しかし精神症状は、“もともとの性格”や“ストレス耐性”とは異なる変化として現れることが多く、「いつから」「どのように」変化したのかを丁寧に聴くことが必要です。
🗣️ 例:「昔から明るい性格だったのに、最近ほとんど口をきかない」
→ 性格ではなく、抑うつ状態の可能性あり
🧠 なぜ症状に“違和感”を覚えるのか
精神症状は、私たちの常識や経験から外れた内容(例:被害妄想、幻聴)を含むことが多いため、「どこまでが現実で、どこからが症状か」が分かりにくいのが特徴です。
だからこそ、以下のような問いかけが重要です:
- 本人はその体験を「現実」と感じているのか?
- その症状が生活にどのような影響を与えているのか?
- 症状の出現にパターン(誘因・時間帯・環境)があるか?
これらの情報を集め、症状の“意味”や“深刻さ”を多面的にとらえる視点が、精神症状を診る第一歩となります。
2. 症状を整理する5つの視点|ICD/DSMに基づく観察軸
精神症状は「幻覚」「妄想」「気分の落ち込み」など単語で語られることが多いですが、実際の臨床では、それぞれの症状をどのように“観察・分類”するかが診断や治療の出発点になります。
DSM-5-TRやICD-11などの診断基準では、精神症状を以下のような主要な5つの領域(視点)からとらえています。
① 認知(Cognition)
現実をどのようにとらえているか。記憶・注意・知能・見当識・判断力などの変化を含む。
- 例:見当識障害(時間・場所・人が分からない)
- 例:記憶障害(直前の会話を繰り返す)
② 知覚(Perception)
実際には存在しないものを「ある」と感じる体験。幻覚や錯覚、過敏・鈍麻なども含む。
- 例:幻聴(誰もいないのに声が聞こえる)
- 例:錯視(カーテンの柄が人に見える)
③ 思考(Thought)
思考の内容や進み方の異常。妄想や強迫思考、観念奔逸、思考途絶などが含まれる。
- 例:被害妄想(誰かに監視されている)
- 例:思考化声(自分の考えが声になって聞こえる)
④ 感情(Mood / Affect)
気分(主観)と感情(他者から観察される情緒)の異常。うつ状態・躁状態・不安・情緒不安定など。
- 例:気分が沈み「死にたい」と語る
- 例:些細なことで怒鳴る・泣き出す(感情制御困難)
⑤ 意欲と行動(Volition / Behavior)
行動の活性・抑制、衝動性、意欲の低下、興奮・緊張・逸脱行動などを含む。
- 例:無気力で日常動作ができない
- 例:突発的に外へ飛び出す(衝動行動)
これらは互いに独立して存在することもあれば、複合して現れることもあります。
たとえば「幻聴が聞こえて怖いから、外出できず、気分も沈んでいる」という場合、
- 知覚異常(幻聴)
- 感情の異常(不安・抑うつ)
- 意欲の低下(外出困難)
という複数の視点からとらえることで、より正確な全体像を把握できます。
🧩 ワンポイント:症状=「言葉」+「文脈」
精神症状は、「声が聞こえる」「死にたい」「不安だ」といった言葉の裏に、どのような状況・背景で起きているのかを常に意識することが重要です。
その人にとって、どんな意味を持つ体験なのかを問いながら、5つの視点を軸に“症状の地図”を描いていきましょう。
3. 評価の実際:初期面接でどこまで聴くか
初診の精神科面接は、限られた時間の中で多くの情報を引き出す必要があります。しかし、精神症状の評価は「深く」「正確に」行おうとするあまり、話が拡散し、全体像がつかみにくくなることもあります。
だからこそ、はじめの面接では“すべてを聴こうとしない”ことがむしろ重要です。限られた範囲で、症状の核となる部分を探り、全体像をおおまかにとらえることが目的となります。
🗂️ 初回面接で確認したい5つのポイント
- ① 主訴(今、困っていること)
できるだけ本人の言葉で。「夜が眠れない」「頭の中で声がする」「誰かに見られている気がする」など - ② 発症時期と経過
「いつから」「突然か徐々にか」「きっかけは何か」「良くなったり悪化したりする波があるか」 - ③ 日常生活への影響
仕事や学校、家事、対人関係にどのような支障が出ているか - ④ リスク評価
自殺念慮・自傷行為・他害リスク・生活能力の著しい低下 - ⑤ 身体疾患・薬物・アルコールの関与
合併疾患・内服薬・物質使用歴の確認
🔍 症状を掘り下げるフレーズ例
症状を聞き出すとき、抽象的な言葉にとどまらず、「具体的にどんなふうに?」を意識して掘り下げることが重要です。
- 「最近気分が落ち込んでいて……」
→「その気分は、どんな時に強くなりますか?」 - 「誰かに見られている気がする」
→「実際に誰かの姿を見ましたか? どんな状況ですか?」 - 「死にたいと思うことがある」
→「それは、漠然とした気持ちですか? 具体的にどうしたいと思いますか?」
言葉の裏にある“意味”を探るためには、一つの症状に対して複数の角度からたずねる視点が必要です。
🧠 NVC的アプローチの応用
非暴力コミュニケーション(NVC)の視点では、相手の語る言葉の背後にある「感情」と「ニーズ(大切にしたいもの)」を理解する姿勢が重視されます。
精神科面接でも、表現の奥にある不安・孤独・葛藤をくみ取るために、評価ではなく共感を基盤とした対話を心がけることが、安心感や自己開示につながります。
📘 ワンポイント:国試では“評価の順序”が問われる
国試では、症状の詳細そのものよりも、「どこから・どう評価を進めるか」というアプローチの優先順位が問われることが多くなっています。
📝 例:「幻聴を訴える患者。まず確認すべき事項はどれか?」
→ 解答:身体疾患・薬物の影響(除外診断)
面接の構造化と優先順位づけの力は、国家試験・日常診療どちらにも役立つ重要なスキルです。
4. 精神症状を「他者と共有する」ための記録と表現
精神症状は本人の内面の体験に根ざした“主観的”なものであり、そのままでは他人と共有することが困難です。
だからこそ、臨床の場では「記録」や「表現」のしかたが非常に重要になります。
適切な表現ができなければ、正確な引き継ぎも、適切な診断や治療方針の共有も難しくなってしまいます。
📄 主観的な言葉を、客観的に表現する
研修医や非専門医が精神科的な記録で迷いやすいのが、「主観と客観のバランス」です。
たとえば、以下のように整理できます:
| 患者の発言 | 記録例(主観の記述) | 記録例(観察による記述) |
|---|---|---|
| 「誰かに監視されている」 | 被害妄想を訴える | 誰かに見られていると繰り返し話す。周囲を警戒し続けている |
| 「声が聞こえる」 | 幻聴の訴えあり | 一人で笑ったり返答する様子あり。「命令されている」と説明 |
| 「生きてても仕方ない」 | 希死念慮を自覚 | 抑うつ的な表情。死にたい気持ちが頻回に出現していると述べる |
このように、主観的体験の“内容”と、それがどのように“観察されたか”を分けて記録することで、より正確な情報共有が可能になります。
🧠 誤解されやすい言葉の使い方
精神科領域では、以下のような用語が医学的に正しく使われていないケースも少なくありません:
- 「幻覚」⇔ 実際は幻視・錯視・妄想との混同
- 「うつ状態」⇔ 落ち込んでいること全般ではなく、診断基準あり
- 「せん妄」⇔ 認知症との違いが不明確な記録が多い
こうした点も、正確に使い分けられる表現力を持っておくことで、専門医との連携がスムーズになります。
📘 医師国家試験でも「記述表現」が問われる
国試では、「○○と記載されていた場合、考えられる診断はどれか」といった症状記述→疾患推定の問題も頻出です。
📝 例:「幻聴により会話が遮られる。外界との接触が希薄で独語がある」
→ 疾患:統合失調症の可能性
「どう記録するか」は、「どう診断するか」「どう伝えるか」につながっています。
5. 国試で問われる症状の整理|よく出る5パターン
精神症状は主観的であいまいな印象を持たれがちですが、医師国家試験では非常に明確な視点で問われています。それは、実際の診療でも誤診や見落としにつながりやすいためです。
ここでは、国試で繰り返し問われている代表的な5つの症状について整理します。
① 幻覚(特に幻聴)
- 聞こえるはずのない声が聞こえるという体験
- 統合失調症の中核症状として頻出
- 国試では「思考化声」「命令する声(命令幻聴)」などの用語が問われる
📝 例題:「頭の中の声に命令されて行動している」
→ 答:命令幻聴 → 統合失調症を考える
② 妄想(被害・関係・誇大など)
- 根拠のない確信に基づく誤った信念
- 被害妄想・関係妄想・誇大妄想などの分類がある
- 境界性パーソナリティ障害、統合失調症、せん妄との鑑別が問われやすい
📝 例題:「テレビが自分のことを話しているように感じる」
→ 答:関係妄想
※ 幻覚・妄想については、今後の疾患別アプローチ(統合失調症・せん妄・認知症・気分障害など)でより詳しく取り上げていきます。
③ 抑うつ気分・希死念慮
- 「気分が沈む」「死にたい」といった訴え
- 気分障害(うつ病)とパーソナリティ・反応性抑うつとの鑑別
- 自殺企図のリスク評価が頻出
📝 例題:「最近ずっと気分が沈んでいて、死にたいと思うことがある」
→ 選択肢:安全確保 → 保護入院・家族への説明
④ 不安・恐怖・パニック症状
- 不安障害(GAD)、パニック症、PTSD、強迫性障害(OCD)との鑑別が重要
- 自律神経症状(動悸・発汗)や回避行動も含めて問われる
📝 例題:「人前に立つと心臓がバクバクして動けない」
→ 答:社交不安障害(SAD)
⑤ せん妄・認知症との鑑別
- 高齢者に多い意識障害の1つ
- せん妄は“急性発症・日内変動・幻視”が特徴
- 認知症と混同しやすく、国試でも頻出の鑑別ポイント
📝 例題:「入院後2日目の夜間、興奮し『虫がいる』と騒ぐ」
→ 答:せん妄(夜間・幻視・急性経過が鍵)
🧠 ワンポイント:知識ではなく“症状の意味”を問われる
国試では単に症状の名称を答えるだけでなく、「その症状が何を意味しているのか」「どう対応すべきか」が問われます。
このシリーズでは、こうした誤答の多い選択肢・つまずきやすい症状の理解についても、各記事で随時取り上げていきます。
6. まとめ:症状から診断へ、そして支援へ
本記事では、精神症状をどのように捉え、記録し、診療につなげていくかという視点を紹介してきました。
精神症状は、その多くが本人の主観的な体験に根ざした“見えにくい症状”です。しかし、以下のようなステップを意識することで、非専門医でも確かな評価と対応が可能になります。
✅ 精神症状を診る5つのポイント(おさらい)
- 「主観と客観のあいだ」にある症状としてとらえる
- ICD/DSMに基づく5領域(認知・知覚・思考・感情・行動)で整理する
- 初診時は全体像を把握する面接構造を意識する
- 記録では観察と訴えを区別し、共有可能な表現に落とし込む
- 国試でよく出る症状は、意味・文脈・鑑別を含めて理解する
🧭 非専門医・家庭医にとっての意味
精神症状の初期評価は、何も“精神科専門医の専売特許”ではありません。むしろ初診外来や在宅医療、総合診療・家庭医療など「誰が最初に気づけるか」がカギになります。
本シリーズでは、症状の理解から鑑別・治療方針・支援制度までを段階的に学べるよう構成しています。次回の記事では、具体的な症状(幻覚・妄想・抑うつ・不安 など)を取り上げ、さらに深く掘り下げていきます。
症状別のアプローチ(統合失調症、うつ病、認知症、せん妄など)を、疾患別アプローチ編で詳しく扱います。
🔗 ▶ 次の記事を読む:精神症状のとらえ方|5つの視点と診断プロセス
📚 関連記事リンク
📖 参考文献
- 精神科ハンドブック(全5章). 2022-2024. 精神科診療実践研究会. https://psychiatry-handbook.com
- DSM-5-TR: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, American Psychiatric Association, 2022.
- ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics, World Health Organization, 2022.
- 医師国家試験問題解説書 QB 精神科(第119〜118回) 医学書院.
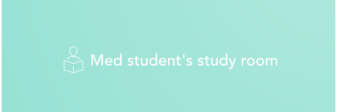
ピンバック: 【精神科プライマリケア│疾患別「双極性障害」】 ー Med Student's Study Room