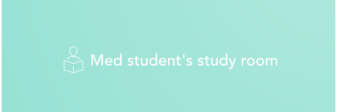【不安・パニック障害|医学生・研修医のための実践ガイド】
この記事で学べること
- プライマリケアの現場でよく出会う「不安症」「パニック発作」の実践的な診療アプローチ
- DSM-5とICD-11の診断基準に基づく「正しい見立て」の力
- SSRIやベンゾジアゼピン系薬剤の適切な使い方とそのリスク管理
- 認知行動療法(CBT)を中心とした非薬物療法の考え方
- 家庭医・非専門医として対応できる範囲と、精神科専門医に紹介すべきタイミング
この記事はこんな人におすすめ
- 不安や動悸を訴える患者を前に「何科の病気か迷ってしまう」ことがある研修医
- SSRIや抗不安薬を使うのに躊躇してしまうプライマリケア医
- 精神科との連携のタイミングに悩む総合診療医
- OSCE・CBT・国家試験での出題対策をしたい医学生
記事の位置づけと使用教材
本記事は、精神科ハンドブック第3〜4章を中核教材とし、DSM-5-TRやICD-11に準拠した診断知識、ならびに
日本うつ病学会ガイドライン(不安障害)、APAガイドライン(米)、NICEガイドライン(英)などの国際的推奨を適宜参照しながら、
医学生・研修医・非専門医にとって実践的な内容に整理しています。
2. 不安症とは何か?|定義と診断カテゴリーの整理
不安とは何か?
不安(Anxiety)とは、将来の出来事に対する漠然とした恐れや緊張を指します。
明確な対象のある「恐怖(fear)」とは異なり、不安はより内在的で持続的な情動体験であり、身体症状(動悸・発汗・呼吸困難など)を伴いやすいのが特徴です。
不安症(Anxiety Disorders)の定義
DSM-5-TRにおいて「不安症群(Anxiety Disorders)」は、以下の症候を主とする精神疾患の集合と定義されます:
- 持続的かつ過度な不安や心配
- 予期不安、回避行動、身体症状(自律神経反応)
- 社会的・職業的機能への明らかな支障
なお、DSM-5では強迫症(Obsessive-Compulsive Disorder)や心的外傷後ストレス障害(PTSD)は「不安症群」から分離され、独立した診断群に分類されています。
DSM-5における主な「不安症群」疾患
- 全般性不安症(GAD)
- パニック症(Panic Disorder)
- 広場恐怖症(Agoraphobia)
- 社交不安症(Social Anxiety Disorder)
- 限局性恐怖症(Specific Phobia)
- 分離不安症(Separation Anxiety Disorder)
- 選択性緘黙(Selective Mutism)
ICD-11における分類との違い
| 分類体系 | 特徴的な違い |
|---|---|
| DSM-5-TR(米国・APA) |
|
| ICD-11(WHO) |
|
不安・抑うつ・身体症状のオーバーラップ
不安症はしばしばうつ病や身体表現性障害(身体症状症)と重なり、鑑別が難しくなることがあります。
特に初診外来では「動悸・息苦しさ・胃部不快感」などの身体症状を訴えて受診する例が多く、背景に不安症があることを見落とさない視点が重要です。
3. パニック障害とパニック発作の違い
「パニック発作(Panic Attack)」とは?
DSM-5-TRでは、パニック発作を以下のように定義しています:
- 突発的に出現し、数分以内にピークに達する強い不安のエピソード
- 以下の13症状のうち4つ以上が同時に現れる
- 動悸、心悸亢進、または脈拍の増加
- 発汗
- 身震い、または震え
- 息切れ感、または息苦しさ
- 窒息感
- 胸痛、または胸部不快感
- 吐き気、または腹部不快感
- めまい、ふらつき、頭が軽くなる感じ、気が遠くなる感じ
- 現実感消失(現実でない感じ)、または離人感
- コントロールを失うこと、または気が狂うことに対する恐怖
- 死ぬことへの恐怖
- 感覚麻痺、またはうずき感
- 寒気、またはほてり感
多くは10〜30分で自然軽快し、明確な誘因がないことも特徴です。
「パニック障害(Panic Disorder)」の診断基準
DSM-5-TRによれば、パニック障害とは以下の基準を満たすものです:
- 繰り返される予期しないパニック発作(前述の定義)
- 発作のうち少なくとも1回の発作の後1か月以上にわたり、以下のうち1つ以上が続いている:
- さらなる発作についての持続的な懸念または心配
- 発作に関連した意味や結果(失神・コントロール喪失など)についての心配
- 発作を回避しようとする行動の著しい変化(外出忌避、交通機関の回避など)
- 発作は物質(薬物・カフェインなど)または他の身体疾患(甲状腺機能亢進症、心疾患など)によるものではない
パニック発作とパニック障害の関係
すべてのパニック発作がパニック障害にあたるわけではありません。
例えば、うつ病・PTSD・社交不安症の一部としてパニック発作が生じることもあります(=診断名は異なる)。
「過換気症候群」との違いに注意
- 「過換気症候群(Hyperventilation Syndrome)」は医学的に明確な診断概念ではない
- 多くの過換気エピソードが、実はパニック発作や不安症の症状として生じている
- パニック発作は通常30分以内に自然軽快し、再発・回避行動・予期不安がなければ障害ではない
- 「数時間続く」「誘因がはっきりしている」場合は他疾患を疑う(例:中毒・てんかん・敗血症)
診断名として「過換気症候群」を安易に使うことは、治療機会を逃すリスクにもつながるため注意が必要です。
4. 疾患別分類|不安症のバリエーション
不安症は「1つの病気」ではない
「不安症(Anxiety Disorders)」は、単一の病名ではなく、多様な症候群の総称です。
DSM-5-TRでは以下の7疾患が不安症群に分類されており、それぞれで発症様式・予期不安・回避行動の性質が異なります。
DSM-5-TRにおける不安症の分類と特徴
| 疾患名 | 主な特徴 | 発症時期 |
|---|---|---|
| パニック症 | 突発的な強い恐怖感・身体症状を伴う発作 | 10代後半〜30代 |
| 全般性不安症(GAD) | 慢性的で漠然とした過剰な心配・緊張 | 20代〜 |
| 社交不安症 | 他人の注視に対する強い恐怖・緊張 | 思春期〜20代 |
| 限局性恐怖症 | 特定対象(高所・動物・注射など)への過剰な恐怖 | 小児〜 |
| 広場恐怖症 | 公共交通・人混みなど「逃げられない場所」への恐怖 | 10代後半〜 |
| 分離不安症 | 愛着対象からの分離への過剰な不安 | 小児(成人でも診断可能) |
| 選択性緘黙 | 特定状況での発語困難(家庭では話せるが学校では話せない等) | 幼児〜学齢期 |
ICD-11との違い|PTSD・強迫症の扱い
DSM-5では以下を不安症群から除外しています:
- 強迫症(OCD) →「強迫・関連症群」として独立
- PTSD・急性ストレス障害 →「外傷およびストレス関連障害群」へ
一方、ICD-11では以下を「不安・恐怖関連障害(6B0)」群に含めています:
- 恐怖症群(Phobic Anxiety Disorders)
- パニック症、GAD
- 社交不安、分離不安
- OCD、PTSD、身体症状症も同グループ内で関連性を記述
実臨床での見立ての工夫
- 「不安が強い」といっても、その内容・持続時間・誘因により疾患が異なる
- パニック症と広場恐怖は併存率が高い(特に公共交通機関の回避など)
- 社交不安と回避性パーソナリティ障害、GADとうつ病はしばしば鑑別困難
研修医・非専門医としては「診断を1つに決める」よりも、「どの軸が強いかを見極めて支援の方針を立てる」視点が重要です。
5. 病態と心理モデル|なぜパニックは繰り返されるのか?
不安はどのように強化されるのか?
パニック発作や不安症は、「不安 → 身体症状 → 誤った認知 → さらなる不安」という悪循環を形成しやすいのが特徴です。
この構造を可視化したのが、いわゆる認知行動療法(CBT)における不安の悪循環モデルです。
このモデルを理解することで、単なる「気のせい」ではなく、脳の反応と行動の学習によって症状が強化されていく構造を説明できます。
CBTにおける「不安の悪循環」モデル
例:電車内で心臓がドキドキ → 「心臓発作では?」と誤解 → さらに不安増強 → 逃げ出す → 「やっぱり危なかった」と誤学習 → 次も電車が怖くなる
- 症状そのものよりも、「症状の解釈」が不安を引き起こす
- 「逃げる」「避ける」行動が短期的には安心を与えるが、不安を維持する主因になる
- 曝露療法ではこの回避行動と安全確認行動を徐々に減らす
生物学的仮説|脳と神経伝達物質の関与
不安・パニック発作の背景には、以下のような神経学的・神経化学的要因が関与していると考えられています:
- 扁桃体(amygdala)の過活動:恐怖の処理・過覚醒反応
- 前頭前皮質の抑制機能低下:危険評価の抑制が効かない
- セロトニン系の不均衡:SSRIが有効な理由の1つ
- ノルアドレナリンの過剰放出:交感神経の過活動と動悸・過呼吸
これらの要因により、不安が「本当に危険であるかのように」脳が反応し、パニック発作を繰り返すとされています。
精神科と家庭医の視点の統合
- 精神科:脳・神経・行動モデルに基づき治療戦略を設計
- 家庭医:症状の背景にある心理・社会的ストレッサーの同定に強み
不安症の理解は、生物・心理・社会(bio-psycho-social)モデルを基礎として、「なぜこの人に、今このような症状が現れたか?」を考えることから始まります。
6. 初診時によくある訴えと場面(実症例)
症状は「心の悩み」としてではなく、「身体の異常」として現れる
不安症やパニック発作の患者は、精神症状を自覚して受診するとは限りません。
多くの場合、以下のような身体症状や急性のエピソードを主訴として受診します。
📍 救急外来での出会い
「夜中に突然、心臓がバクバクして、息ができなくなって…このまま死ぬかと思った」
→ 意識は清明、バイタル正常、心電図・採血も異常なし。翌日にまた同様の発作で再来。
- パニック発作の典型例
- 「原因不明」の身体症状が繰り返されるとき、背景に不安症を疑う視点が重要
📍 プライマリケア外来での出会い
「最近ずっと胸が苦しいんです。循環器には異常ないって言われたんですけど…」
「仕事中に急に息苦しくなって、そのまま早退することが増えました」
- 症状が持続的・慢性的なケースはGADや広場恐怖症も視野に
- 「どんな場面で起こるか」「何を避けるようになったか」を具体的に問う
📍 精神科への紹介初診での場面
「内科で検査しても異常がないと言われ、紹介されました」
「過換気って言われたけど、それだけじゃない気がして…」
- 既に複数の診療科を受診している「ドクターショッピング型」も多い
- 「この症状に名前がつくのか」「良くなるのか」への説明責任と安心形成が重要
🔍 見逃さないための視点
- 精神的背景に気づきにくい患者でも、「いつ・どこで・どんな時に」を具体的に聴くことでトリガーが明らかになる
- 心因性と決めつけず、身体疾患の除外を丁寧に行うことが信頼関係形成につながる
- 「死ぬかと思った」「このまま倒れると思った」はパニック発作の重要な手がかり
7. Step 1:問診のポイントとRed Flag
「発作」はどのように起きるのか?
まずは症状の出現様式・経過・誘因を丁寧に把握します。
以下のようなポイントを押さえることで、「パニック発作らしさ」が見えてきます。
- 突然の発症か?(何分でピーク?どのくらい続く?)
- 誘因はあるか?(特定の場所、状況、対人など)
- 反復性があるか?(何度も繰り返している?)
- 予期不安があるか?(「また起こるのでは…」という恐怖)
- 回避行動があるか?(外出・通勤・乗り物を避けている?)
症状の具体例を引き出す質問
- 「息苦しくなった時、それは何分くらい続きましたか?」
- 「その時“自分がどうなる”と思いましたか?」
- 「最近、そのようなことが起きるのを避けるようになったことはありますか?」
Red Flag(身体疾患を見逃さない)
以下のような症状がある場合は、身体疾患(内科・神経・中毒など)の除外が必要です。
- 持続時間が30分以上続く
- 意識障害を伴う
- 左右差のある神経症状
- 発熱、脱水、代謝異常の疑い
- 服薬・サプリ・カフェイン・ドラッグ使用歴
特に見逃しやすいのが以下の疾患です:
- 甲状腺機能亢進症(手指振戦・体重減少・発汗)
- 褐色細胞腫(高血圧・発作性頭痛・発汗)
- アスピリン中毒(耳鳴り・過換気・嘔吐)
- てんかん(意識障害・奇異な行動・健忘)
- 不整脈(心電図での頻脈・心房細動)
Red Flag(精神疾患の見落としに注意)
以下の点がある場合は、他の精神疾患の可能性も検討します。
- 現実検討力の低下(妄想・幻聴) → 統合失調症・気分障害
- 抑うつ症状が前景 → うつ病 with パニック発作
- トラウマや解離 → PTSD・解離性障害
- 人格の不安定さ → 境界性パーソナリティ障害
問診まとめ:3つの構造的確認
- いつ起きるか?(予測可能 vs 不可)
- どんな症状か?(DSM-5の13症状に照らす)
- どんな思考・行動があるか?(「また起きるのでは?」という予期不安・回避)
8. Step 2:身体診察・鑑別
身体診察の目的:重篤な身体疾患の除外
パニック障害や不安症は診断基準上「除外診断」であるため、まず身体疾患を否定する必要があります。
以下の項目は、初診時に必ず確認すべき所見です。
バイタルサイン・観察項目
- 血圧・脈拍:不整脈、起立性低血圧、頻脈
- 呼吸数・SpO₂:呼吸困難や過換気の客観評価
- 体温:感染症や中毒、悪性症候群の鑑別
身体診察で注目すべき所見
| 診察領域 | 注目ポイント | 鑑別に挙がる疾患 |
|---|---|---|
| 頸部触診 | 甲状腺腫・振戦・眼球突出 | バセドウ病(甲状腺機能亢進症) |
| 心音・リズム | 不整脈、頻拍 | 心房細動、期外収縮 |
| 肺音 | ラ音・呼吸困難 | 肺塞栓、気管支喘息 |
| 意識・姿勢 | 反応鈍さ・混乱・せん妄 | 低血糖、中毒、てんかん |
| 神経所見 | 片麻痺・眼振・構語障害 | 脳卒中、てんかん発作後 |
必ず鑑別したい身体疾患(重要鑑別リスト)
- 肺塞栓症(PE):呼吸困難、頻呼吸、動悸、リスク因子(D-dimer, Wells score)
- 甲状腺機能亢進症:動悸・手の震え・体重減少(TSH, FT4)
- 褐色細胞腫:発作性高血圧・頭痛・発汗(三徴)
- アスピリン中毒:過換気・耳鳴り・代謝性アシドーシス(血液ガス・サリチル酸濃度)
- てんかん発作後:健忘・舌咬傷・脱力・意識障害
- 心疾患:不整脈・狭心症・心筋症(ECG, 心エコー)
補足:中毒・薬剤性も見逃さない
- カフェイン・アルコール・ニコチン・覚醒剤
- 甲状腺薬・ステロイド・気管支拡張薬・降圧薬
- 抗うつ薬(SNRI/MAOI)による賦活症候群
薬剤歴・市販薬・サプリ・エナジードリンクの使用歴なども丁寧に聴取しましょう。
9. Step 3:診断と評価
診断は「除外診断」+「症候パターンの同定」
不安症やパニック障害の診断は、まず重大な身体疾患を除外した上で、DSM-5-TRやICD-11の診断基準に基づく症候パターンを確認していきます。
初診時に診断名を確定できなくても、「パニック様発作が繰り返されている」「予期不安や回避行動がある」といった構造を把握することが重要です。
DSM-5-TRによる「パニック障害」の診断基準(再掲)
- 突発的かつ予測不能なパニック発作が繰り返される
- 発作の少なくとも1つの後に、以下のいずれかが1か月以上持続
- さらなる発作に対する持続的な心配
- 発作の意味や結果(死ぬのでは・気が狂うのでは)への不安
- 回避行動・ライフスタイルの変化
- 症状は物質(薬物・中毒)や身体疾患では説明されない
補助的に使える評価尺度(スクリーニング)
プライマリケアでは、診断の補助として以下のような簡便なスケールも有用です:
- GAD-7:全般性不安障害に特化した7項目尺度(0〜21点)
- PDSS-SR:パニック症の重症度を自己記入式で評価(Panic Disorder Severity Scale)
- HADS(Hospital Anxiety and Depression Scale):不安・うつを同時にスクリーニング
あくまで参考ツールであり、最終的な診断は臨床像・背景情報と統合して判断する必要があります。
患者への説明|診断時の言葉がけ
- 「今の症状には“パニック発作”という医学的な名前がついています」
- 「これは命に関わる病気ではなく、適切に治療すれば良くなるものです」
- 「一時的に身体に強い不安反応が起きる状態で、“不安の回路”が過敏になっていると考えられます」
診断名を伝えることで安心感と今後の治療方針の理解を促すことができ、早期の治療導入にもつながります。
10. Step 4:治療戦略①:薬物療法(SSRI・BZD)
基本方針:第一選択はSSRI、BZDは短期使用
- 第一選択はSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)
- ベンゾジアゼピン系薬(BZD)は、急性期の補助的頓用として限定使用
- 治療継続は少なくとも12か月を目安にする(早期中断で再発リスク↑)
第一選択薬:SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)
SSRIは、パニック症・全般性不安症・社交不安症など多くの不安症に対する第一選択薬として各国ガイドラインで推奨されています。
| 薬剤名 | 初期用量 | 特徴 |
|---|---|---|
| セルトラリン(ジェイゾロフト®) | 25〜50mg | 比較的安全域が広く、プライマリケアで使いやすい |
| エスシタロプラム(レクサプロ®) | 10mg | 眠気少なく、薬物相互作用が少ない |
| パロキセチン(パキシル®) | 10mg | 抗不安作用強いが、離脱症状に注意 |
効果発現までには2〜4週間程度かかるため、初期に「効かない」「不安定になった」と感じる患者も多く、副作用への事前説明が極めて重要です。
補助的に使用される薬剤:ベンゾジアゼピン系(BZD)
BZDは即効性がある反面、依存やせん妄のリスクがあるため、原則として短期間・必要最小限の使用が基本です。
- 初期導入時の不安増悪の緩和目的
- 頓用処方(as needed/PRN)として使用
- 長期連用・常用は避ける(特に高齢者)
BZDの薬剤プロファイル(作用時間と副作用)
| 薬剤名 | 作用時間 | 抗不安作用 | 筋弛緩 | 催眠作用 |
|---|---|---|---|---|
| エチゾラム(デパス®) | 短時間 | 超強 | 強 | 強 |
| ロラゼパム(ワイパックス®) | 短時間 | 強 | 中 | 中 |
| アルプラゾラム(ソラナックス®) | 中時間 | 強 | 弱 | 中 |
| ジアゼパム(セルシン®) | 長時間 | 強 | 強 | 強 |
プライマリケアでの頓用では、アルプラゾラムやロラゼパムを少量処方する例が多いですが、高齢者ではジアゼパム・エチゾラムは避けるべきです。
処方時の注意点と説明
- SSRIは1日1回、朝または夕に継続投与
- 副作用(吐き気・不眠・性機能障害など)について事前に説明
- BZDは連日投与ではなく、必要時頓用(as needed/PRN)で処方
- 「薬だけに頼らず、並行して心理的支援も重要」という方針を伝える
各国ガイドラインにおける薬物治療の位置づけ
| ガイドライン | 第一選択 | BZDについて |
|---|---|---|
| 日本うつ病学会(不安障害編) | SSRI(推奨度A) | 短期併用可・長期使用不可(依存リスク) |
| APA(米国精神医学会) | CBTまたはSSRI | 単独使用は推奨せず |
| NICE(英国) | 心理療法(CBT)が優先、次にSSRI | 原則使用せず/特殊状況のみ短期 |
11. Step 5:治療戦略②:心理療法(CBTなど)
心理療法の役割:症状の「意味づけ」そのものを変える
薬物療法が「脳の反応」を調整するのに対し、認知行動療法(CBT)は、症状を維持する考え方・行動パターンにアプローチします。
パニック障害や社交不安症においては、各国ガイドライン(NICE、APA)でも第一選択の治療として位置づけられています。
認知行動療法(CBT)の基本構造
CBTでは以下の3点を明確化し、誤った「認知(解釈)」と「回避行動」を修正していきます:
- 状況(きっかけ):どのような場面で不安が出るか
- 認知(思考):「死ぬのでは」「逃げられないのでは」など
- 行動:回避、安全確認、過呼吸など
この悪循環のループを視覚化し、少しずつ行動を変えることで、認知の柔軟性を高めていきます。
主要なCBT技法とその目的
| 技法 | 目的 | 例 |
|---|---|---|
| 暴露療法(exposure) | 不安を引き起こす状況に徐々に慣れる | 電車に短時間だけ乗る→徐々に時間延長 |
| 認知再構成法 | 不適切な自動思考を修正する | 「死ぬかもしれない」→「過去も大丈夫だった」 |
| 身体感覚への暴露 | 心拍・息切れなど身体感覚に慣れる | その場でジャンプして心拍数を上げる練習 |
| 呼吸法・筋弛緩法 | 自律神経系を安定させる | 腹式呼吸・漸進的筋弛緩 |
家庭医・非専門医ができる心理的支援
- 「今の症状には仕組みがある」ことを伝える → 安心形成と精神化
- セルフモニタリング(発作日誌・症状記録)を促す
- CBT実施可能な医療機関・心理士への紹介
- 予備知識として、患者向けCBT本・ワークブック(ex.『不安と上手に付き合う本』)の紹介も可
日本でCBTを受けられる場所
- CBT研修を受けた精神科医・臨床心理士
- 認知行動療法センター(国立精神・地域拠点)
- 保険適応は医師によるCBTのみ(2025年現在)
実際に専門機関へつなぐ際には、発症経過・主な不安症状・予期不安・回避行動の有無などを明確に記載した紹介状があるとスムーズです。
12. Step 6:患者説明と心理教育|“なぜこの症状が出たのか”を理解してもらう
不安症への理解は「回復への第一歩」
不安症の患者は、「自分はおかしくなったのでは」「もう元には戻れないのでは」という深い恐怖を抱えて受診していることが多くあります。
そのため、医療者からの説明で「この症状は理解可能で、治療可能なものである」と伝えることが極めて重要です。
心理教育(Psychoeducation)の主な目的
- 症状の正体を言語化する → 「構造の見える化」
- 誤学習・誤解釈を修正する → 「安全の再学習」
- 患者の受け身姿勢を変える → 「能動的な自己管理」
説明のキーワード:患者にこう伝える
| 説明テーマ | 伝え方の例(言い換え) |
|---|---|
| 症状の構造 | 「体の異常ではなく、脳が“危険だ”と誤作動している状態です」 |
| 自然経過 | 「ほとんどのパニック発作は、数十分で自然に収まります」 |
| 予後 | 「正しい治療で、多くの人が元の生活に戻れています」 |
| 治療の仕組み | 「薬は“脳のセンサーの感度”を調整するものです」 「行動練習で、“安全だった経験”を積み直すことが大事です」 |
| 回避行動 | 「避けるほど“怖い場所”になってしまうので、少しずつ慣らしていきましょう」 |
患者との共有に使える図・資料
- 不安の悪循環モデル(症状 → 誤認知 → 行動強化)
- 症状記録シート・発作日誌:きっかけ・思考・行動を記録
- 厚労省・CBT支援センターのリーフレットなども有用
※画像付き資料や図解ツールを用いると、非専門医でも心理教育を短時間で効果的に実施できます。
「精神化(mentalization)」の視点
身体化されていた症状(動悸・息切れ)に「心理的意味づけ」を与えることで、患者自身が自分の感情や身体状態に気づき、対処する力を育てることができます。
「“死ぬかも”という強い不安が起きた時、あなたの体は“全力で逃げる準備”をしていたんです」
13. Step 7:予後と経過、再発予防|フォローアップのポイント
予後は良好。ただし「再発しやすい」特性に注意
パニック障害や不安症は、適切な治療により約7〜8割が改善する予後良好な疾患です。
一方で、再発しやすい特性があり、治療中止やストレス再燃により「ぶり返し」やすいことが知られています。
経過観察時のポイント
- 症状の推移(GAD-7、発作日誌、来院時の語り口)
- 予期不安・回避行動の減少があるかどうか
- 服薬アドヒアランスと副作用モニター
- 生活習慣やストレス源の変化(職場・家庭・対人)
発作の消失だけでなく、「生活範囲がどれだけ回復しているか」「患者が自分の症状をどう捉え直せているか」が重要です。
再発しやすい状況・特徴
- 服薬を自己判断で中断
- 強い生活環境ストレス(転職、離婚、妊娠など)
- もともとの不安傾向・回避パーソナリティ
- CBTや心理教育を受けず、症状理解が進んでいない
家庭医・かかりつけ医としての支援の工夫
- 定期的な“安心確認”:再燃予防のためのフォローアップ(1〜2か月毎)
- 症状が軽くなっても支援継続:「症状がない=治癒」ではない
- 再発時にどうするかを事前に共有:Relapse Planをつくる
「また不安になってきたら、○○の薬を使って、それでも落ち着かなかったら相談に来てください」
再発予防の患者指導・セルフケア
- 適度な運動、規則正しい生活
- カフェイン・アルコール・ニコチンの管理
- ストレスコーピング(書き出す、話す、休む)
- 症状記録アプリ・呼吸法の継続練習
「治療を受けてよくなる」だけでなく、「自分で再発を防ぐ方法を持つ」ことが長期的な回復には重要です。
14. 精神科紹介の判断基準|非専門医が診られる範囲と限界
非専門医が診療可能な範囲
軽〜中等症の不安症(とくにGAD・社交不安・軽度のパニック障害)であれば、非専門医や家庭医でも十分にマネジメント可能です。
- 発作頻度が低い/予期不安が軽度
- 回避行動が限定的(電車・人混みなど特定シーンのみ)
- 併存疾患が少ない(抑うつ・発達障害などの合併がない)
- 患者が治療意欲・洞察を保っており、信頼関係が構築できている
紹介を検討すべき場面
- 発作が頻回で生活に支障を来している(欠勤、登校拒否、外出困難など)
- 強い予期不安・広範な回避(電車、職場、外出全般など)
- うつ病・PTSD・解離などの鑑別困難な併存疾患が疑われる
- 患者が希死念慮や自傷行為を訴えている
- 薬物乱用・服薬管理困難・家庭内暴力など社会的リスクが高い
紹介時に添えるべき情報(紹介状に明記を)
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 主訴・経過 | 発作が何回あり、どのような状況で起きたか |
| 既往歴 | 精神科・内科・救急外来の受診歴など |
| 検査・治療歴 | 心電図・採血で除外済/SSRIを1ヶ月内服など |
| 生活背景 | 職場・家族・支援体制など |
| 希望の共有 | 「今後もこちらでフォローを希望」 or 「専門治療に移行希望」 |
精神科との連携を前提とした初期対応
- いきなり紹介するのではなく、まず初期評価・支援・除外診断を行った上で連携を依頼
- 本人の不安と希望も尊重し、「精神科=怖いところ」という先入観を和らげる言葉がけが重要
- 診療情報提供書には「ここまで行った上で紹介」したことを記載する
15. 身体疾患との合併・誤診リスク|不安の背後に隠れた疾患を見逃さない
“心因性”と決めつけず、身体疾患の除外を怠らない
不安症やパニック障害の初診時には内科疾患と極めて類似した身体症状を呈することが多いため、「心の問題」として片づけず、身体疾患を除外するプロセスが不可欠です。
不安様症状を呈する主な身体疾患
| 鑑別疾患 | ポイント | 診断のヒント |
|---|---|---|
| 甲状腺機能亢進症 | 動悸・焦燥・不眠・体重減少 | TSH・FT4測定/手指振戦・眼球突出 |
| 褐色細胞腫 | 発作性高血圧・頭痛・発汗 | カテコールアミン・画像評価(CT/MRI) |
| アスピリン中毒 | 過換気・耳鳴・嘔気・傾眠 | 血中サリチル酸・AG代謝性アシドーシス |
| 低血糖発作 | 動悸・冷汗・不安感・健忘 | 空腹時血糖・食後のタイミングで評価 |
| 肺塞栓症 | 呼吸苦・頻脈・不安・SpO₂低下 | D-dimer、Wellsスコア、造影CT |
| てんかん(部分発作) | 急な恐怖感・異常感覚・健忘 | 脳波、MRI、舌咬傷、脱力の有無 |
| 心疾患(不整脈・狭心症) | 動悸・胸部不快感・不安 | 心電図、ホルター、運動負荷試験 |
不安症に併存する身体疾患を見逃さない
不安症が「原因」である場合もあれば、「何らかの身体疾患によって二次的に不安を引き起こしている」場合もあります。
- 不安症 + 貧血 → 息苦しさの悪化
- 不安症 + 頻脈症候群(POTS) → 歩行時に強い不安感
- 不安症 + 頻尿/下痢 → IBS・過敏性膀胱・内分泌疾患など
患者が「不安によるものですか?」と尋ねてきた時ほど、本当に不安症だけなのかを再評価する姿勢が重要です。
心身両面からの診立てが家庭医の強み
- 精神症状と身体症状の交錯領域を丁寧に診る
- 患者の「病気の物語(illness narrative)」を聞く
- 不安が“どこに宿っているか”を身体感覚レベルで捉える
「頭では“心の問題かも”と分かっていても、体が“やっぱり何かある”と感じている」
16. 国試対策まとめ|鑑別・語句・典型例の整理
まず押さえるべき5疾患
以下の5つは国試でも繰り返し出題される「不安症状の鑑別疾患」です:
- パニック障害(Panic disorder)
- 全般性不安症(GAD)
- 社交不安症(SAD)
- 心気症/身体症状症
- PTSD/解離性障害
DSM-5-TRによる「パニック障害」の診断基準:頻出内容
- 発作は突然・ピークまで数分・10分以内に自然軽快
- 13の症状から4つ以上で発作と診断(例:動悸、発汗、震え、息切れ、胸痛、めまい、死の恐怖)
- 予期不安・行動変化が1か月以上持続
- 身体疾患や薬剤・物質の影響でない
重要鑑別と鑑別ポイント
| 疾患 | 症状の特徴 | 鑑別ポイント |
|---|---|---|
| パニック障害 | 突然・反復性の発作(動悸・呼吸困難・死の恐怖) | 発作時は意識清明/診察時異常なし/予期不安あり |
| GAD | 慢性的な不安・緊張が続く(半年以上) | 心配の対象が多岐にわたる/身体症状は軽度 |
| PTSD | トラウマ体験後の再体験・過覚醒 | 誘因が明確/1か月以上持続 |
| 甲状腺機能亢進 | 動悸・焦燥・手指振戦・体重減少 | TSH・FT4測定で判別可能 |
| てんかん | 恐怖・健忘・発作性行動 | 舌咬傷・EEG異常・脱力 |
頻出!重要用語・語句まとめ
| 語句 | 意味・使い方 |
|---|---|
| 予期不安 | 「また発作が起こるのでは」という不安。診断上・治療導入時に重要。 |
| 広場恐怖(agoraphobia) | 「逃げられない」ことへの恐怖 → 電車、劇場、群衆などを避ける |
| 回避行動 | 不安を避けようとする行動(例:外出しない)。慢性化リスク因子。 |
| 精神化(mentalization) | 症状に意味づけを与える力。家庭医の支援場面で問われる。 |
| 誤認知・安全確認行動 | 「死ぬのでは」「心臓が止まるのでは」→ 繰り返すことで不安が維持される。 |
薬剤の国試ポイント
- 第一選択はSSRI(セルトラリン、エスシタロプラム、パロキセチンなど)
- SSRIは効果発現に2〜4週間/初期悪化あり → 事前説明が重要
- ベンゾジアゼピン(BZD)は短期頓用のみ可/依存性・せん妄に注意
- 高齢者にはBZD禁忌(ふらつき・転倒)
典型的な国試パターン(例題)
23歳女性。夜間突然、動悸・発汗・呼吸困難が出現。「このまま死ぬのでは」と感じ、救急受診。診察時には症状消失。
→ パニック障害を疑い、SSRI導入+予期不安と回避の有無を確認
40代女性。胸苦しさ・しびれ・ふらつきで循環器外来を繰り返し受診。異常なく「精神的なもの」と言われ不信感。
→ 身体疾患除外+丁寧な心理教育で“精神化”を図る
暗記より「構造理解」が差をつける
国試では単なる知識よりも「症状構造・誤認知・回避・治療へのつなげ方」の理解が問われます。
精神科に苦手意識がある人ほど、ここで“実践につながる整理”が役立ちます。
実際の問題(国家試験より)
● 119D49|パニック障害の治療選択
【設問】突然の動悸・発汗・呼吸困難を繰り返す25歳女性。診察時は異常なし。
→ 正解:SSRI。典型的なパニック障害の症候構造。
● 111D54|社交不安症の症例
【設問】人前で話すと喉が詰まる22歳男性。日常生活に支障あり。
→ 正解:SSRI+抗不安薬。場面限定型の社交不安症に対する基本治療。
● 103G67|うつ病 vs パニック障害
【設問】息苦しさ・動悸で受診した中年男性が「自分はもうだめ」と発言。
→ 正解:うつ病とパニック障害の併存可能性を考慮。
17. 制度・社会資源|診断書・自立支援・職場対応
診断書の記載|「病名より機能」に焦点を
パニック障害・不安症に対する診断書は、病名だけでなく「どのような場面で・どんな支障があるか」を記載することが重要です。
- 例)「電車通勤時に発作症状が生じ、通勤継続が困難な状況」
- 一時的な休職やリモート勤務への配慮が可能となる
- 復職に向けた段階的な支援(短時間勤務など)も検討対象
自立支援医療制度(精神通院)
精神科通院に対して自己負担が1割となる制度。パニック障害や社交不安症も対象となります。
- 申請には医師の診断書(自立支援用)と市区町村窓口での申請が必要
- 更新は1年ごと。症状が継続する場合は更新手続きを
- 通院先が複数ある場合、すべて記載が必要
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)
原則としてパニック障害やGAD単独では該当しにくいが、長期間にわたり就労や日常生活に支障が大きい場合は検討。
- 等級は1〜3級(症状の程度・生活障害度による)
- 交通機関の割引・就労支援などの対象になる場合あり
就労支援・学校・職場への対応
- 発作が日常生活・通勤・就学に支障をきたす場合、診断書とともに生活調整の提案が有効
- 学校:保健室登校・時差通学など段階的支援が検討される
- 職場:リモート・在宅・時短勤務・休職制度など、医師のコメントが活きる
- 再発リスクを考慮し、復帰は「生活リズムの安定」や「認知行動の獲得」が前提
家族・周囲のサポート資源
患者本人のみならず、家族への説明・教育も重要な治療の一部です。
- 症状の理解、対応の仕方(過干渉・過保護の回避)
- 再発リスクへの備え、生活全体の調整
- 地域によっては精神保健福祉センター、保健師、訪問看護も活用可能
連携の視点:家庭医・非専門医ができること
- まず診断と説明、薬物療法の導入、制度の紹介まで行える
- 必要に応じて、精神科専門医・産業医・校医・MSWとの連携
- 紹介時には就労・生活状況の具体的情報を添えるとスムーズ
18. まとめ|診療の流れとツール整理
パニック障害・不安症の初期対応フローチャート
- 急性症状か?(発作/救急外来)
→ 意識・バイタル・器質疾患の除外が最優先 - 既往歴と誘因を確認
→ 発作の反復性・回避・予期不安の有無 - DSM-5基準で診断確認
→ パニック障害、GAD、SADなどの鑑別を意識 - 薬物療法の導入(SSRI+BZD頓用)
→ 初期悪化の説明+治療同意 - 生活指導・制度支援・精神科紹介
→ 通院継続が困難な場合や重度例では連携を
診療で役立つ「使える表現」一覧
- 「発作は一過性のもので、すぐにおさまることが多いです」
- 「この症状は“命に関わる病気”ではなく、体の過剰な反応です」
- 「薬は徐々に効いてくるので、最初の2週間は悪化しやすいですが心配いりません」
- 「無理に外出するより、“少し行って帰ってくる”という練習が大事です」
家庭医・非専門医が押さえるべき3点
- ① 診断は「除外+構造理解」で十分できる
- ② 治療はSSRIと説明がセット。初期対応が今後を左右
- ③ 制度・診断書・生活支援を含めた「全人的支援」こそ家庭医の強み
参照リンク・資料
【Appendix. Medical English Expressions|医療英語表現・用語】
Useful Medical Expressions
- panic attack:パニック発作
- generalized anxiety disorder (GAD):全般性不安障害
- social anxiety disorder (SAD):社交不安障害
- anticipatory anxiety:予期不安
- agoraphobia:広場恐怖症
- somatic symptoms:身体症状
- hyperventilation:過換気
- reassurance:安心感/安心を与える説明
Layman’s Terms & Idioms
- “I feel like I’m going to die.”(死にそうな感覚)
- “My heart’s racing out of nowhere.”(突然、心臓がバクバクする)
- “I can’t breathe when I panic.”(発作時は息ができない)
- “I’m afraid to leave the house.”(外に出るのが怖い)
Medical English Glossary
| 英語表現 | 日本語訳 |
|---|---|
| shortness of breath | 息苦しさ・呼吸困難 |
| palpitations | 動悸 |
| dizziness / lightheadedness | めまい/ふらつき |
| tightness in the chest | 胸の圧迫感 |
| tingling sensation | しびれ感 |
| cognitive behavioral therapy (CBT) | 認知行動療法 |
【Reference|参考文献・関連記事リンク】
📘 診療ガイドライン・教科書
- 日本精神神経学会. 精神科診療ガイドライン 統合失調症・不安症・うつ病 2023年版
- American Psychiatric Association. DSM-5-TR: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed. Text Revision, 2022.
- WHO. ICD-11: Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders (Version 2024)
- NICE Guideline CG113. Generalised anxiety and panic disorder in adults: management, 2011 (updated)
- UpToDate. Panic disorder in adults: clinical features and diagnosis(最終アクセス:2025年7月)
- 厚生労働省. 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築ガイドライン(2022年)
- 日本プライマリ・ケア連合学会. プライマリ・ケアにおける不安障害対応指針, 2019年
- 『精神科ハンドブック』第3章「疾患別アプローチ」/第4章「薬物治療」
🔗 関連記事(内部リンク)
- ▶ 精神科診療の初期アプローチ:家庭医のための7ステップ
- ▶ 動悸(Palpitations)|器質疾患との鑑別ポイント
- ▶ 胸痛(Chest Pain)|パニック障害との鑑別に要注意
- ▶ 失神・意識消失(Syncope)|てんかん・不安・低血糖の見分け方