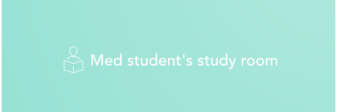この記事で学べること
- 「うつ状態」を前にしたときの初期対応・鑑別・紹介基準を整理します
- 医師国家試験でも頻出の「うつ状態=うつ病?」という疑問に答えます
- 家庭医・非専門医として“どこまで対応するか”の実践指針を提示します
- 「問診で何を聴くべきか」「薬を出す前に何をすべきか」を症例ベースで解説します
この記事はこんな人におすすめ
- うつ病と診断された患者をどう支えてよいかわからない初期研修医
- 不眠や食欲低下を訴える患者に精神的背景があるか迷っている外来医
- 「気分が落ち込む」と訴える高齢患者への対応に不安がある在宅医
- 精神科との連携・紹介のタイミングを見極めたい家庭医・総合診療医
- 国家試験のうつ病問題を“臨床的に”理解したい医学生
この「疾患別シリーズ」について
本記事は、精神科ハンドブック(全5章)をベースにした「疾患別アプローチ」シリーズの一つです。
特に医学生・非専門医・初期研修医を対象に、精神科診療の“苦手意識”を克服するための実践的な視点を提供しています。
本稿では、最も出会う頻度の高いうつ病を取り上げ、「どこまで診るか」「どう見極めるか」に焦点を当てて解説します。
💡 まだ総論記事(第1〜3記事)をお読みでない方は、ぜひ先にご覧ください:
1. はじめに|なぜ“うつ状態の見極め”が難しいのか?
「最近、やる気が出ないんです」
「夜眠れないし、ご飯も美味しく感じません」
「仕事に行くのがつらくて、休みがちなんです」
こうした訴えに出会ったとき、あなたなら何を考えるでしょうか?
「これはうつ病だろうか?」「でも、検査値は正常だし…」
「休職を勧める?薬を出す?それとも様子を見るべき?」
— 精神科医以外の多くの医師が、“うつ状態の見極め”に悩むのは当然です。
🔍「うつ病」という診断の曖昧さ
DSM-5-TRでは、うつ病(Major Depressive Disorder)は9つの診断基準に基づいて診断されます。
しかし、そのどれもが主観的であり、他の疾患と重複しやすいのが現実です。
たとえば以下のような例は日常茶飯事です:
- 不眠・食思不振 → 甲状腺機能異常や悪性腫瘍でも起こる
- 抑うつ気分 → 悲哀反応・ストレス反応・適応障害との区別が難しい
- 高齢者の意欲低下 → 認知症や薬剤性うつ、社会的孤立の可能性も
🧠「うつ=精神の病」ではない
うつ状態は、身体疾患・薬剤・心理社会的ストレスなどさまざまな要因のアウトプットです。
そのため、「うつ=即うつ病」とは限らないという視点が重要になります。
実際、医師国家試験でも「どのような背景によりうつ状態を呈したか」を問う問題が頻出です。
⚠ 誤診・見逃し・過剰診断のリスク
- 誤診:うつ病と思っていたら認知症や内分泌疾患だった
- 見逃し:「気のせい」と判断していたら重度のうつだった
- 過剰診断:正常な悲しみ反応をうつ病と誤って投薬した
こうしたリスクを避けるには、家庭医・非専門医に求められるのは「精神疾患の診断」ではなく、「うつ状態の背景を探る姿勢」です。
診断に飛びつくのではなく、「見極める力」を養うことを目的とします。
2. まず押さえるべき視点:うつ状態とうつ病は違う
うつ状態(depressive state)と、うつ病(major depressive disorder)は同じではありません。
「落ち込んでいる」「元気がない」という訴えがあっても、それが必ずしも病的なうつであるとは限らず、その背景にある“状況”や“意味”を捉える視点が欠かせません。
📘 うつ状態とは?
うつ状態とは、抑うつ気分・興味の喪失・易疲労感・不眠・食思不振などの、主観的な症状が一定期間持続している状態を指します。
これらは、以下のようなさまざまな病態に伴って現れることがあります:
- 正常な悲嘆(grief)や喪失反応
- 職場・家庭のストレスによる反応性の気分変調
- 身体疾患(例:がん、甲状腺機能異常、パーキンソン病など)
- 薬剤(例:β遮断薬、ステロイド、インターフェロンなど)
📙 うつ病とは?
うつ病はDSM-5-TRで定義される診断基準を満たす精神疾患です。
9つの症状のうち5つ以上が2週間以上持続し、かつ社会的・職業的な機能障害を伴うことが必要です(詳細は後述)。
したがって、「うつ状態」=「うつ病」と即断することは危険です。
🔍 医師国家試験でも頻出の視点
以下は国試でよく問われる「見極め」のポイントです:
- 正常な反応:家族の死別による悲しみは「うつ状態」でも「うつ病」とは限らない
- 器質的疾患:高齢者の意欲低下・不眠が実は「甲状腺機能低下症」だった
- 適応障害:明確なストレス因があり、6か月以内に出現した軽度の気分変調
🧭 診断より「背景」を探る姿勢
家庭医・非専門医にとって重要なのは、「うつ状態を見たらまず何を疑うか?」という診断推論の視点です。
そのためには、「精神疾患かどうか」より先に、“うつ状態を呈する他の原因”を広く検討するアプローチが求められます。
過剰診断や見逃しを防ぐ第一歩になります。
3.Step 0:うつ病の診断基準(DSM-5-TR)
DSM-5-TRでは、うつ病(Major Depressive Disorder, MDD)は以下の9つの症状のうち、5つ以上が2週間以上持続し、日常生活に支障をきたしていることを診断基準としています。
🧠 主要な9項目(うち2つは必須症状)
- 抑うつ気分(ほとんどの時間、ほとんどの日)★
- 興味または喜びの著しい減退(ほとんどの活動で)★
- 食欲の減退または増加、体重の変化
- 不眠または過眠
- 精神運動性の焦燥または制止(観察可能なもの)
- 易疲労性または気力の減退
- 無価値感または過剰な罪責感
- 思考力や集中力の減退、決断困難
- 死についての反復思考、自殺念慮・企図
★:1または2のいずれかは必ず含まれている必要があります。
📌 その他の条件(全てを満たす必要あり)
- 上記症状が社会的・職業的機能に著しい障害を与えている
- 物質や身体疾患による影響で説明できない
- 双極性障害(躁状態など)のエピソードがない
🎯 実臨床での注意点
- “あてはまりはするが、意味が異なる”という場合がある
- 例:癌の終末期に抑うつ症状を伴っていても、全体像は悲嘆反応かもしれない
- 症状の持続だけでなく、その「質」と「文脈」が重要
📝 医師国家試験で問われるポイント
- 「診断基準の構成項目」は頻出(暗記でなく構造理解が重要)
- 「双極性障害との鑑別」や「身体疾患との除外」が出題される
- 「症状の生活障害性」や「希死念慮の有無」が問診で問われる
臨床では常に“その症状が何を意味しているか”という文脈理解が求められます。
4. Step 1:うつ状態の患者に出会ったときの問診
「気分が落ち込む」「眠れない」「食欲がない」と訴える患者さんに出会ったとき、“何をどこまで聴くか”は非専門医にとって最大のポイントです。
🎯 初期評価で確認したいこと
診断を急ぐ前に、まずは次の4点を整理しておくと実践的です:
- 症状の程度(どのくらい生活に影響を及ぼしているか)
- 発症時期と誘因(明確なストレス?突発的?)
- 精神疾患の既往(うつ・双極性・統合失調症など)
- 自殺念慮や希死念慮(早期評価が必須)
🗣 聴取すべき具体的な項目
- 「最近、何か生活で変化やストレスはありましたか?」
- 「夜は眠れていますか?早く目が覚めてしまうことは?」
- 「食欲はどうですか?体重の変化は?」
- 「物事への興味や楽しみが減ったと感じますか?」
- 「死にたいと思うことはありますか?」
これらはDSM-5-TRの診断基準と対応しており、診断の手がかりだけでなく、治療方針の判断材料にもなります。
📝 OSCEでも問われる「うつ状態」の対応
OSCE(Objective Structured Clinical Examination)では、うつ状態の患者に対して「共感を示しつつ、精神的背景を適切に探れるか」が評価されます。
以下に、OSCE対策・英語診療も含めた症候別記事を紹介します:
OSCEでは、過剰な共感や曖昧な言葉は避け、明確な質問・構造化された面接が求められます。
💡 聴取は「評価」と「支援」の入口
問診の目的は、「うつ病か否か」ではなく、その人の苦しみの輪郭を丁寧に描き出すこと。
精神的な主訴をもつ患者に対して、“言語化を支援する”ような聴取が、第一歩となります。
その声の背景にある“意味”を掘り下げる姿勢が、誤診・見逃しを防ぐ鍵となります。
5. Step 2:身体所見と鑑別診断|まず除外すべき病態は?
精神症状を呈する患者でまず重要なのは、「精神疾患ではない原因を除外する」という視点です。
抑うつや無気力が見られたとしても、それが本当に精神疾患なのか?
身体疾患の一症状として出現しているのではないか?
まずこの確認を怠らないことが、誤診を防ぐ第一歩です。
🧩 よくある鑑別疾患
- 内分泌疾患:甲状腺機能低下症、副腎不全、糖尿病
- 神経疾患:パーキンソン病、脳血管障害、てんかん後抑うつ
- 悪性腫瘍:食欲低下・体重減少・易疲労感などが先行
- 感染症:結核・HIV・梅毒・COVID後遺症
- ビタミン欠乏:VitB12欠乏、葉酸欠乏、鉄欠乏
💊 薬剤によるうつ状態(Drug-induced depression)
以下の薬剤はうつ症状を引き起こす可能性があります:
- インターフェロン
- ステロイド
- β遮断薬・Ca拮抗薬
- ベンゾジアゼピンの離脱
- 抗コリン薬(過活動膀胱治療薬など)
新規開始薬・中止薬の確認は必須です。
👀 身体診察で確認したいポイント
精神症状だからといって診察を疎かにせず、以下のような“所見の異常”に注意を払いましょう:
- 甲状腺腫大、除脈・浮腫 → 甲状腺疾患
- 皮膚色素沈着・低血圧 → Addison病
- 筋硬直・仮面様顔貌 → パーキンソン病
- 神経所見の左右差 → 器質性疾患(脳血管障害など)
🔬 検査で確認すべき項目
- 甲状腺機能(TSH, FT4)
- 副腎皮質ホルモン(朝のコルチゾール)
- 血算・鉄・VitB12・葉酸
- 感染症スクリーニング(HIV, RPRなど)
- CT/MRI(神経症状があれば)
「うつ状態が精神疾患かどうか」よりも「身体疾患の可能性を除外したかどうか」です。
6. Step 3:検査・血液・画像|うつ病は「除外診断」から始まる
うつ病の診断において検査は直接的な診断根拠になりませんが、器質的・内科的疾患の除外という意味で非常に重要です。
特に、DSM-5-TRにおいても「他の医学的疾患では説明できないこと(C基準)」が明記されており、精神症状の裏に身体疾患が潜んでいないかを確認するのがStep 3の目的です。
🔍 ルーチンで行いたいスクリーニング検査
| カテゴリ | 項目 | 目的・意義 |
|---|---|---|
| 内分泌 | TSH, FT4 | 甲状腺機能低下症(特に高齢・女性) |
| 電解質・代謝 | Na, Ca, BUN, Cr | 高Ca血症、腎不全、低Naによるうつ様症状 |
| 栄養 | Vit B12, 葉酸 | ビタミン欠乏による抑うつ・認知低下 |
| 肝機能 | AST, ALT, γ-GTP | アルコール性変化・肝性脳症の除外 |
| 感染症 | 梅毒, HIV | 慢性感染や中枢病変のスクリーニング |
これらはすべて正常であって初めて「うつ病かもしれない」と判断できる、と言っても過言ではありません。
🧠 器質性疾患の除外に画像検査が必要な場合
以下のような状況では、頭部画像(CT/MRI)を考慮します:
- 高齢者で初発の抑うつ(前頭葉萎縮・脳血管障害の可能性)
- 急激な性格変化や脱抑制
- 神経学的徴候を伴う場合(失調・歩行障害・構音障害など)
また、正常圧水頭症や脳腫瘍などの器質的疾患は、内科医・救急医が拾うべき異常でもあり、精神科紹介前の重要な判断材料になります。
📌 ポイント:精神症状だけで「うつ病」と決めつけない
Dr.faxスライドでも繰り返し強調されているように、うつ病は診断名ではなく「仮説」からスタートするものです。
特に初診患者・高齢者・慢性疾患患者では、検査を省略しない姿勢が安全な医療につながります。
7. Step 4:鑑別診断と除外すべき精神疾患
うつ病の診断は、「うつ状態=うつ病」と決めつけず、他の精神疾患・二次性うつ状態を丁寧に除外するところから始まります。
特に、非専門医による“抗うつ薬の早期投与”が、状態を悪化させるリスクもあるため、鑑別診断の整理は極めて重要です。
🎯 うつ状態の4象限分類(精神科ハンドブックより)
精神科ハンドブックでは、うつ状態を以下の4象限で分類し、対応の違いを整理しています:
| 象限 | 病態の特徴 | 対応 |
|---|---|---|
| A | うつ病エピソード(単極性) | 抗うつ薬 ± 精神療法 |
| B | 双極性うつ(躁の既往・家族歴) | 気分安定薬 ± 抗うつ薬 |
| C | 二次性うつ(身体疾患・薬剤など) | 原因治療を優先 |
| D | 適応障害・環境反応性 | 支持的介入・環境調整 |
初診外来で見逃しやすいのは、特にB(双極性うつ)とC(二次性うつ)です。
📌 鑑別すべき代表的疾患
- 双極性障害: うつ病と誤診されやすい。躁状態の既往や家族歴に注意。
- 適応障害: 明確なストレス因子あり。症状が慢性化しない点が鑑別のカギ。
- 身体疾患による二次性うつ: 甲状腺機能低下症、脳血管障害、がんなど。
- 薬剤性うつ: インターフェロン、ステロイド、ベンゾジアゼピンの離脱後など。
- 統合失調症の陰性症状: 意欲低下・表情の乏しさが主。幻覚・妄想の有無で鑑別。
- 認知症: 高齢者ではうつ状態が前景に出ることあり(仮性認知症)。
🧠 DSM-5-TRのB〜E基準も鑑別のヒントに
DSM-5-TRでは、うつ病の診断に以下のような除外規定が含まれています:
- B基準: 社会的・職業的機能の著しい障害
- C基準: 他の疾患・物質の影響で説明されない
- D基準: 著しい苦痛があること(主観的なつらさ)
- E基準: 喪失反応(死別など)のみではない
これらは鑑別診断のヒントにもなる視点です。
💡 ここがポイント:双極性障害の見逃しに注意
Dr.faxスライドでも繰り返し強調されていたように、初診時に双極性障害の可能性を見逃すと、抗うつ薬で悪化するリスクがあります。
以下のような背景がある場合には、双極性の可能性を意識し、安易な抗うつ薬単剤投与は避けましょう:
- うつ状態が若年で発症(10〜20代)
- 症状が急激かつ重度(希死念慮など)
- 家族歴に躁うつ病がある
- 過去に軽躁エピソードを疑う言動あり
📘 幻覚や妄想がある場合は?
精神病性うつ、統合失調症、認知症などとの鑑別が必要です。
これらは、今後の「疾患別記事:統合失調症/認知症」の中で詳細に扱います。
「抑うつ状態=うつ病」と安易に決めつけず、全体を丁寧に見立てる姿勢が非専門医には求められます。
8. Step 5:重症度評価と緊急性の見極め
うつ病は多様な重症度で現れ、軽症から自殺リスクの高い重症例まで幅広く存在します。初診時にその「深刻さ」を見極めることが、安全な診療の第一歩となります。
🔍 評価の観点はこの3つ
- 生活への支障度(仕事・学業・対人関係)
- 自殺念慮・希死念慮の有無
- 身体的影響(食欲・体重減少、睡眠障害)
これらは単なる“チェック項目”ではなく、患者の「困っていること」を引き出す手がかりでもあります。
📋 重症度評価のスケール(PHQ-9)
非専門医でも使いやすい評価スケールとして、PHQ-9(Patient Health Questionnaire-9)が推奨されます。
- 簡便で、質問紙形式
- 点数で重症度を数値化
- 初診と経過観察の比較に有用
| PHQ-9スコア | 重症度の目安 |
|---|---|
| 0〜4点 | 正常〜最小限のうつ |
| 5〜9点 | 軽症うつ病 |
| 10〜14点 | 中等症 |
| 15〜19点 | 中等度〜重症 |
| 20点以上 | 重症うつ病 |
なお、PHQ-9の設問9(死にたいと思うか)が「2=ほとんど毎日」の場合は、特に注意を要します。
🚨 自殺リスクの評価
自殺念慮の評価は、「訊くこと自体が悪影響を及ぼすことはない」とされています。
以下のようなフレーズで、自然にリスクを評価しましょう:
- 「最近、死にたいと思うことはありますか?」
- 「実際に計画を立てたり、準備をしたことはありますか?」
- 「誰かに相談できていますか?」
自殺念慮がある場合は、以下の点も併せて確認しておくと支援の優先度が明確になります:
- 自殺の具体的計画(手段、場所、時期)
- 過去の自殺未遂歴
- 支援者の有無(家族・友人)
- 物質使用(アルコール、薬物)
💡 専門医への紹介が必要な状況
以下のいずれかに該当する場合は、初期治療よりも専門医紹介を優先します:
- 明確な自殺計画がある、または直近で自殺未遂がある
- 現実感の乏しい妄想・幻覚を伴う
- 拒食・絶食により生命的危機がある
- 家族の支援が乏しく、独居・高齢者など社会的リスクが高い
「重症そうだから怖い」ではなく、「どの支援が必要か」を考える視点が大切です。
9. Step 6:治療方針と初期対応|抗うつ薬だけじゃない治療の全体像
うつ病の治療は、単に「抗うつ薬を出すこと」ではありません。重症度、背景、患者の希望に応じた治療戦略を立てる必要があります。
ここでは、CQ(Clinical Question)をもとに、エビデンスと現実的な方針を整理します。
🎯 CQ1:すぐに薬を出すべき?どのくらいの症状なら治療介入が必要?
- 軽症例では経過観察・心理教育・生活指導のみで改善することも。
- 中等症以上なら薬物治療+精神療法を検討。
ガイドラインでも「すべてのうつ状態に抗うつ薬は不要」と明記されています。患者の負担、希望を踏まえた丁寧な説明がカギとなります。
💊 抗うつ薬を使う場合のポイント
抗うつ薬の開始は、双極性の除外後に慎重に。非専門医が扱う場合、以下の点に注意が必要です:
- 第一選択は SSRIまたはNaSSA(副作用が比較的少ない)
- 効果発現は 2〜4週間以降(効果判定を急ぎすぎない)
- 中止は 少なくとも症状改善後6か月は継続(再燃予防)
- 離脱症状や副作用のモニターも忘れずに
最初の投与量は「半量から開始」が原則です(特に高齢者)。
📌 非専門医が処方する際の注意点
- 躁転に注意: 「元気になったように見える」が実は軽躁状態のことも
- 副作用の把握: 患者の訴えを「主観」として切り捨てない
- アドヒアランス: 「飲んだり飲まなかったり」が最もリスク
そのため、初診で抗うつ薬を処方するかどうかは慎重な判断が必要です。
🧠 CQ2:薬以外にできることは?
非薬物療法も重要です:
- 心理教育: 「うつ病は回復する」こと、「焦らず休む」ことの重要性
- 生活指導: 睡眠・栄養・運動・日中の活動のリズムを整える
- 簡易な認知行動療法(CBT)要素: 自責の思考に気づく、日記をつける など
また、支援制度の案内(自立支援医療、傷病手当金など)も、医師の重要な役割の一つです。
📝 よく使われる初期薬剤(例)
| 薬剤 | 分類 | 特徴 |
|---|---|---|
| セルトラリン(ジェイゾロフト) | SSRI | 不安症状にも有効、安全域広い |
| ミルタザピン(リフレックス) | NaSSA | 食欲不振・不眠が強い人に有効 |
| エスシタロプラム(レクサプロ) | SSRI | 副作用が少なく使いやすい |
これらは副作用プロファイルや患者背景に応じて使い分けます。
非専門医でもできる「傾聴・説明・支援」は、薬に勝る治療となることもあります。
10. Step 7:副作用と薬剤選択のポイント|“効く”だけで選ばない
抗うつ薬は「どれを選んでも効く」が基本ですが、副作用や患者背景によっては選択が治療の明暗を分けることもあります。
このステップでは、非専門医が押さえておくべき「副作用マップ」と薬剤の選び方のコツを整理します。
🔄 SSRI / SNRI / NaSSAの副作用比較
| 薬剤群 | 主な副作用 | 特徴的な注意点 |
|---|---|---|
| SSRI | 消化器症状(悪心・下痢)、性機能障害、アクチベーション | 自殺念慮がある患者では慎重に(特に若年) |
| SNRI | SSRIに加えて、血圧上昇、動悸 | 高血圧・心疾患には避ける |
| NaSSA(ミルタザピン) | 眠気、体重増加、過食 | 食欲不振・不眠が主症状なら適応 |
患者ごとの症状や副作用プロファイルに応じて、「避けたい副作用から逆算」して選ぶと安全です。
🧠 よくある副作用への対応と説明例
- 悪心: 食後に内服する、1〜2週間で自然軽快することが多い
- 眠気: 就寝前に変更、もしくは薬剤変更を検討
- 性機能障害: SSRIに多く、説明が難しいが継続性に影響するため説明は必要
- アクチベーション: 特に若年で焦燥感が悪化する例あり。慎重投与を。
🔑 処方時の個別対応ポイント
- 高齢者: 薬物動態に配慮し、開始は必ず「半量以下から」
- 若年者: 自殺念慮の悪化リスクに注意。フォローアップの頻度を上げる
- 不眠が主訴: ミルタザピン、トラゾドンなど鎮静系を考慮
- 疲労感・意欲低下: ノルアドレナリン作用のある薬剤(SNRIなど)
- 体重増加を避けたい: NaSSAは慎重に。SSRIやバプロ酸などでも注意
🧪 他剤との相互作用・注意点
- ベンゾジアゼピン(抗不安薬)との併用:短期的には有用、依存性に注意
- 抗てんかん薬、抗精神病薬との併用:専門医管理が基本
- 肝・腎機能障害時:薬剤の代謝・排泄に注意
患者と相談しながら「選ぶ」ことが、治療のスタート地点です。
11. Step 8:非専門医ができること/紹介すべきタイミング
うつ病の診療において、非専門医が「どこまで対応すべきか」「いつ専門医に繋ぐべきか」は常に悩ましい問題です。
ここでは、初期対応からフォローアップまで、非専門医が果たすべき役割を整理し、専門医との連携ポイントを明確にします。
👨⚕️ 非専門医ができること
- 初期評価(重症度、自殺リスク、鑑別の整理)
- 患者教育・心理的支援
- 軽症〜中等症への抗うつ薬の処方・経過観察
- 生活支援(休職・診断書・支援制度など)
- 家族への説明と協力要請
特に、うつ病を“病気として”正しく説明することは、誤解や自責を和らげる大切な支援です。
🏥 紹介を検討すべきタイミング
- 双極性障害が疑われる場合
- 妄想・幻覚を伴う精神病性うつ
- 自殺念慮が強く、具体的計画がある場合
- 治療に抵抗性(2剤以上使用しても改善せず)
- 服薬アドヒアランスが悪く、支援困難な場合
- 発達障害・パーソナリティ障害など合併が複雑
これらは、精神科専門医での包括的な評価と治療調整が必要となることが多いです。
🔄 専門医との連携をスムーズに行うために
- 紹介時には「経過・服薬内容・困っている点」を簡潔にまとめる
- 患者・家族に紹介理由を丁寧に説明し、転院ではなく「協力」として伝える
- 必要であれば、再連携(戻し)も視野に入れる
💬 現場の工夫:「専門医でなくてもできること」を最大化する
精神科医が近隣にいない地域では、家庭医・内科医がうつ病治療の主治医になることも珍しくありません。
その場合、以下のような視点が役立ちます:
- 患者との信頼関係をベースにした「通院支援」
- 診察時間内で完結する簡易な生活指導・認知的介入
- チームでの支援(看護師・薬剤師との連携)
紹介すべきときに躊躇せず、連携できるときに力を出す。それが非専門医の強みです。
12. Step 9:関連制度・診断書・職場・学校への対応
うつ病の診療において、患者の社会生活・経済的背景まで支える視点が重要です。診断だけでなく、制度利用や職場対応まで視野に入れることが、長期的な支援になります。
📄 診断書の記載ポイント
うつ病で診断書が求められる場面:
- 休職(職場への提出)
- 就労制限(短時間勤務や業務軽減)
- 休学・留年申請(学生)
- 障害福祉制度の申請時(自立支援医療など)
記載のポイント:
- 病名は「うつ病エピソード」「気分障害」などで記載
- 「症状により日常生活や業務に支障がある」と明記
- 期間は「〇月〇日〜〇月〇日までの見込み」など具体的に
- 回復の見込みについては「症状の改善に伴い復職・復学可能」と記述可
※家族や本人の意向を十分に確認した上で記載することが基本です。
🧑💼 職場・学校への関わり方
医師が職場や学校と直接やりとりをすることはまれですが、患者と一緒に復職・復学の見通しを共有することが重要です。
支援の具体例:
- 勤務調整(時短勤務、業務の軽減)
- 段階的復職(リワークプログラムの紹介など)
- 教職員との連携(学生相談室やカウンセラーへの橋渡し)
💡 自立支援医療の活用
精神疾患で通院治療を行う場合、「自立支援医療(精神通院医療)」制度を活用することで、治療費の自己負担が原則1割となります。
- 対象:うつ病、双極性障害、統合失調症など
- 必要書類:診断書、申請書、保険証、マイナンバー
- 継続的な治療が必要な患者に特に有用
制度を案内する際は、市町村の窓口(福祉課)での手続きが必要であることも説明しておきましょう。
📝 傷病手当金・障害年金も選択肢に
- 傷病手当金: 健康保険加入者が就労不能となった場合に支給(最大1年半)
- 障害年金: 長期的に就労不能であれば、初診日要件を満たすことで申請可能
いずれも社会保険労務士や医療ソーシャルワーカーとの連携が有効です。
制度の紹介は「社会との橋渡し」であり、医療者にできるもう一つの支援です。
13. Step 10:まとめと実践のポイント|非専門医が担ううつ病診療
うつ病は誰にでも起こりうる、非常に身近な精神疾患です。
しかしその一方で、見逃し・誤診・過剰診断がいずれも起こりやすく、非専門医にとって対応が難しい症候群でもあります。
ここでは、うつ病の診療で押さえるべき実践的なポイントを再確認します。
🧭 うつ病アプローチの10ポイントまとめ
- まずは全身疾患や内科疾患を除外(甲状腺機能・ビタミン・感染症など)
- 自殺念慮の評価は初診時から(聞きにくいが必須項目)
- 発症状況と誘因の整理(ストレス?急性?反応性?)
- 双極性障害との鑑別(躁症状の聴取を忘れずに)
- 抗うつ薬は慎重に導入(いきなり出さない・説明を丁寧に)
- 治療効果は2~4週で判定(早すぎる切り替えはNG)
- 非薬物療法も併用を(心理教育・生活支援・CBT的介入)
- 診断書・制度の説明も医師の大事な仕事
- 紹介は「連携」であり、敗北ではない
- 患者の物語に耳を傾ける(診断名ではなく、その人を診る)
💬 国試で問われやすい“重要ポイント”
- うつ病 vs 双極性障害の鑑別(若年発症・躁症状の有無)
- SSRIの副作用と選択の工夫(消化器症状・性機能障害など)
- 自殺念慮のリスク評価(年齢・性別・既往歴など)
- 治療効果の評価時期(数日で効果が出るわけではない)
- 自立支援医療の対象疾患と申請手順
本記事では、国試で問われた・間違いやすかったポイントを各所に散りばめています。
さらに知識を整理したい方は、精神科ハンドブックの各章や症候別記事をご参照ください。
📎 次に読むべき関連記事
🔗 固定ページへ戻る
📚 参考文献・出典
- 精神科ハンドブック(2023年度版)
- DSM-5-TR(American Psychiatric Association)
- うつ病治療ガイドライン(日本うつ病学会, 2020)
- UpToDate: Unipolar major depression in adults: Assessment and diagnosis
“薬で治す”のではなく、“関わりで支える”。その視点が、あなたの診療を変えていきます。