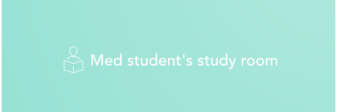Step 0:外傷と熱傷 ― 知っておくべき基本知識と現状
外傷(Trauma)の基礎知識と統計
外傷は、交通事故、転落、刺創、打撲などによって体の構造が急激に損なわれる状態であり、若年層の死因として常に上位に位置しています。
特に10〜40代では、死因の第1位が外傷であり、予防・初期対応・リハビリの3段階すべてが公衆衛生上重要な介入ポイントです。
🚨 世界全体の外傷関連死亡数:約500万人/年
🚗 日本国内でも、毎年約3万人が外傷で死亡(2020年統計)
また高齢者では、軽度な外傷でも致死的になる(=Low-energyでも注意)ことがあり、骨粗鬆症や抗凝固薬の影響も考慮が必要です。
熱傷(Burn)の基礎知識と統計
熱傷は、熱・化学薬品・電流・放射線などの外的因子によって皮膚および深部組織が損傷される状態です。
日本では年間約10万人以上が熱傷で受診し、そのうち重症熱傷(広範囲・深部・特殊部位など)は数千人規模で存在します。
🔥 熱傷の受傷機転TOP3:
1. 熱湯・蒸気(scald)
2. 炎(flame)
3. 接触(contact burn)
高齢者・小児では特に重症化リスクが高く、初期補液と感染予防、呼吸管理が重要です。
なぜ初期対応が重要か?
- 出血・気道閉塞・緊張性気胸・吸入傷など、“silent killer”は外見上わかりにくい
- 適切なABCDE評価がなければ、見逃されてしまう
- 「いかに早く、正確に初期評価と蘇生を行うか」がそのまま救命率に直結する
それでは本編に入りましょう。まずは外傷の初期評価から始まります。
Part 1|外傷(Trauma)編
Step 1:MISTとPrimary Survey(ABCDE・OMI・TAF3X)
1-1. MIST情報の受け取り ― 最初の3秒で全体像を掴む
救急隊や搬送元からのMIST情報は、外傷対応の出発点です。これを聞き逃すと、判断の軸を失いかねません。
| M | Mechanism of injury(受傷機転) |
|---|---|
| I | Injuries found or suspected(損傷部位) |
| S | Signs(バイタル、意識レベル) |
| T | Treatment(現場・搬送中の処置) |
🚑 例:「50歳男性、交通外傷。ハンドルに胸部を強打、GCS14、血圧100/60、酸素3L投与中です。」
このように簡潔かつ重点的な情報を受け取ることで、初期対応の優先順位を素早く判断できます。
1-2. 到着15秒で行う“ぱっと見評価” ― ABCDE+意識・環境
患者が到着した直後、最初の15秒で以下の5つを同時に確認しましょう。
- A(Airway):喉が鳴っていないか、話せているか
- B(Breathing):左右差、呼吸音、呼吸回数
- C(Circulation):皮膚色、冷感、出血の有無
- D(Disability):意識レベル(JCS/GCS)、瞳孔
- E(Environment):脱衣・体温、外傷部位の確認
呼吸音が一側で減弱していた/皮膚が冷たく、橈骨動脈が触れにくい
→ 緊張性気胸 or 出血性ショックの可能性あり!
1-3. Primary Survey ― 命を守るABCDEの本格評価+OMI
一次評価では、各項目を詳細に評価し、同時に処置を並行して行います。
| 項目 | 評価・処置内容 |
|---|---|
| A | 気道確保(頸椎固定を忘れずに!)、吸引、挿管の判断 |
| B | 酸素投与、SpO₂測定、胸郭運動・呼吸音の評価 |
| C | 出血確認、末梢冷感、脈拍数・血圧、IV確保、止血 |
| D | GCS、瞳孔(対光反射・左右差)、血糖測定 |
| E | 全身観察(背部含む)、体温測定、脱衣・保温処置 |
OMI(Oxygen, Monitor, Infusion)
- Oxygen:高濃度酸素(非再呼吸マスクなど)
- Monitor:心電図モニター、SpO₂、バイタル管理
- Infusion:太い静脈ルートを2本以上確保、急速輸液
1-4. 見逃すな!致死的胸部外傷(TAF3X)
外見上は穏やかでも、胸部に致死的外傷が潜んでいる可能性があります。次の6つは必ず評価対象とします。
| 略語 | 内容 |
|---|---|
| T | Tamponade(心タンポナーデ) |
| A | Airway obstruction(気道閉塞) |
| F | Flail chest(動揺胸郭) |
| X1 | Tension pneumothorax(緊張性気胸) |
| X2 | Open pneumothorax(開放性気胸) |
| X3 | Massive hemothorax(大量血胸) |
・Tamponade → 頸静脈怒張+血圧低下+心音減弱(Beckの三徴)
・Tension PTX → SpO₂低下+片側呼吸音減弱+気管偏位
・Flail chest → 吸気時に凹む胸郭(逆の動き)
ここまでで命に関わる外傷の初期評価が完了しました。次は全身状態をより詳しく把握するための「Secondary Survey」へと進みます。
Step 2:Secondary Survey(二次評価と全身観察の基本)
Primary Surveyで命に関わる問題に対応した後は、次に二次評価(Secondary Survey)に進みます。ここでは、見逃されやすい外傷や併存疾患、詳細な全身観察を行い、必要な検査へとつなげていきます。
2-1. AMPLE聴取 ― 迅速に背景をつかむ5項目
患者が話せる状態であれば、以下のAMPLEを聴取しましょう。家族や同乗者・救急隊からの情報も貴重です。
| A | Allergies(アレルギー) |
|---|---|
| M | Medications(内服薬、抗凝固薬など) |
| P | Past medical history(既往歴) |
| L | Last meal(最終飲食) |
| E | Events / Environment(受傷状況、事故現場の様子) |
・抗凝固薬(DOAC、ワルファリン)は必ず確認
・最終飲食は、意識低下時の誤嚥リスクや全麻手術の判断材料になる
2-2. 頭から足までの視触打聴 ― 全身評価のフレームワーク
身体診察は、「頭から足まで」の順に系統的に行いましょう。以下は診察時に見落としやすいチェックポイントです。
- 頭部:頭皮血腫・開放創、耳出血・Battle徴候
- 顔面:鼻骨変形、眼窩骨折、視力・複視
- 頸部:気管偏位、皮下気腫、頸静脈怒張
- 胸部:呼吸音、胸郭変形、Flail chest
- 腹部:圧痛、筋性防御、腹部膨満(FAST対象)
- 骨盤:圧痛・不安定性(両手で軽く圧迫)
- 四肢:末梢神経麻痺、変形、開放創、遠位脈拍
- 背部:log-rollで観察(脊椎圧痛・創傷)
側頭骨骨折などで見られる、耳の後ろの皮下出血斑。脳底骨折の重要なサインの一つ。
2-3. 頸椎評価と固定 ― 背後に潜む脊損を見逃すな
外傷患者では、脊髄損傷を常に想定して動く必要があります。頸椎評価と固定は「やりすぎ」くらいが安全です。
- 意識障害・頭部外傷:頸椎損傷の可能性が高い → 固定優先
- 後頸部圧痛・四肢しびれ:画像評価(CT or MRI)を検討
- 初期対応では:原則として、CTで明らかな損傷が否定されるまでネックカラー継続
背部観察やボード移乗時には、Log-roll(ロール法)を用いましょう。
3~4人で頭頸部を軸に保ち、協調して回転。頭部保持者が号令を出します。
外傷患者の背部を観察・処置するために、患者の身体を軸を保ったまま横向きに回転させる方法です。頸椎損傷を想定しながら安全に観察・移乗を行う際に必須です。
🔧 実施手順(例:4人の場合)
- ① 頭部保持者:最も重要なポジション。頸椎を中間位に保ちつつ、合図(「1・2・3で回します」など)を出す。
- ② 胸部・骨盤:両側で体幹を支え、患者を同期して回転させる。
- ③ 下肢:大腿部・下腿部を安定させて保持。
- ④ 観察・処置者:背部を観察し、創傷や出血・脊椎圧痛などを評価。必要時にボード移乗などを行う。
・頸椎固定は頭部保持者が最優先(移動の最初から最後まで固定を保つ)
・「1・2・3」で全員が同時に協調して動くことが重要
・背部観察後は同様に「1・2・3」で仰臥位に戻す
ここまでで、生命を脅かす外傷だけでなく、潜在的な損傷の評価も完了しました。次のステップでは、「ショックと輸液戦略」へと進んでいきます。
Step 3:ショックの評価と輸液戦略(FAST・TXA・骨盤損傷)
外傷の初期対応で最も重要なのが、ショック状態の早期発見と初期輸液です。明らかな出血が見えなくても、体内で大量出血が進行していることがあります。
このセクションでは、ショックの見抜き方と初期対応、TXAの使い方、骨盤骨折の扱いまでをまとめます。
ショックは37症候にも含まれており、こちらで詳しく解説しています:
ショックの診かた|ABCアプローチとPOCUSによる初期評価・治療戦略
3-1. ショックの定義と身体所見
ショックは、臓器灌流の低下によって生命を脅かす緊急状態です。外傷では出血性ショック(hemorrhagic shock)が最も多く、以下の所見を重視します:
- 皮膚冷感・蒼白・多汗
- 橈骨動脈触知困難(収縮期BP ≒ 80mmHg以下)
- 意識低下(D)・頻脈(C)・尿量低下
若年者や高齢者では、バイタルが“見かけ上正常”でもショックは進行していることがあります。
重要なのは末梢冷感・脈圧低下・尿量などの「末梢所見」です。
3-2. 出血源検索:FASTと骨盤X線
ショックが疑われたら、速やかに体内出血の有無を確認します。特に重要なのが以下の2つです。
🔍 FAST(Focused Assessment with Sonography for Trauma)
- 心嚢、Morison窩、脾周囲、膀胱周囲(ダグラス窩)を確認
- 陽性所見あれば、緊急開腹やIVRを検討
🦴 骨盤XP
- 骨盤輪の開大・不整 → 骨盤内出血を示唆
- FAST陰性でも出血性ショックのときは、骨盤骨折を強く疑う
・大腿骨骨折:1.0〜2.0 L
・骨盤骨折:1.0〜4.0 L以上(致死的)
・下腿骨折:0.5〜1.0 L
・上腕骨骨折:約0.5 L
3-3. 初期輸液と止血戦略
ショックへの対応は、以下の順で進めます:
- 太いルートでの急速輸液(Ringer’s乳酸液など)
- 止血操作:圧迫 → 止血帯 → TXA → IVR or 開腹止血
- 酸素投与・体温管理・尿量モニタリング
出血性ショックが疑われる場合、輸液よりも止血の方が優先されるべきこともあります。
特に骨盤骨折では、骨盤バインダーの即時装着が有効です。
3-4. TXA(トラネキサム酸)の使用
外傷性出血におけるTXAの効果は、CRASH-2試験などで証明されており、可能な限り早期に投与を行います。
- 初回:1gを10分かけて静注
- 維持:その後8時間かけて1g持続静注
- 使用タイミング:受傷後3時間以内が理想
国際多施設ランダム化比較試験。外傷性出血に対してTXAが死亡率を有意に低下させることを示した。
→ 特に早期投与(3時間以内)が重要。
ここまでで、ショックの見極めと緊急対応の全体像がつかめたはずです。次は、損傷の程度や重症度を把握する「スコアリングと特殊症例」へと進みましょう。
Step 4:エネルギー分類と重症度スコア(GCS, ISS, RTSなど)
ここでは、外傷の重症度を客観的に把握するための分類とスコアを紹介します。
受傷機転から全体像をつかみ、スコアを使って専門医への紹介・搬送や予後予測の判断に活かしましょう。
4-1. エネルギー分類:High vs. Low energy trauma
外傷では受傷エネルギーの大きさに応じて、重症度や対応方針が変わります。
🔺 High-energy trauma(高エネルギー外傷)
- 交通事故、高所からの転落、鉄道事故、建物倒壊 など
- 合併損傷が多いため、原則CT撮影を行う(頭部・頸部・胸腹部)
- CTでの「通り魔的拾い上げ」が生命を救うことも
🔻 Low-energy trauma(低エネルギー外傷)
- 転倒、打撲、階段からの転落(特に高齢者)
- 抗凝固薬・高齢者では要注意!
- 「見た目軽症」でも頭蓋内出血・骨盤骨折などが潜んでいることがある
転倒だけでも「ワーファリン内服・高齢者」ならCT適応に。
高齢者では皮膚の下に深刻な損傷があるケースも多く、Low-energy = Low-risk ではない。
4-2. GCS(Glasgow Coma Scale)
GCSは意識レベルを客観的に評価するスケールです。外傷患者では記録と経時変化の観察が重要です。
| 項目 | 評価 | スコア |
|---|---|---|
| E(開眼) | 自発的 | 4 |
| 呼びかけで開眼 | 3 | |
| 痛み刺激で開眼 | 2 | |
| なし | 1 | |
| V(言語) | 見当識あり | 5 |
| 混乱した会話 | 4 | |
| 不適切な発語 | 3 | |
| 理解不能の発声 | 2 | |
| なし | 1 | |
| M(運動) | 命令に従う | 6 |
| 疼痛刺激で部位確認 | 5 | |
| 疼痛刺激から逃れる | 4 | |
| 異常屈曲反応(除皮質) | 3 | |
| 異常伸展反応(除脳) | 2 | |
| なし | 1 |
合計13~15:軽症/9~12:中等症/8以下:重症 → 気管挿管を検討
4-3. ISS(Injury Severity Score)とRTS(Revised Trauma Score)
📊 ISS:外傷部位ごとの重症度評価
身体を6領域(頭部・顔面・胸部・腹部・四肢・体表)に分け、最も重症な3部位のAISスコアを2乗して合計。
ISS ≧ 16で重症外傷とされる。
📈 RTS:生理学的な重症度評価
- GCS・SBP(収縮期血圧)・RR(呼吸数)の3項目を点数化し、合計
- 意識・循環・呼吸の指標として、トリアージや予後予測に有用
・GCS:神経学的評価の基本。初期と経時変化を記録
・ISS:解剖学的損傷の程度。外傷センター搬送判断に使われる
・RTS:生理学的変化の把握。ショックや予後予測に有効
ここまでで外傷のエネルギーと重症度を把握する視点が整いました。次は、特殊な患者背景(高齢者・小児・妊婦など)と、ロール法を含む協調的なチーム対応へ進みましょう。
補足:交通外傷の実践対応 ― 所見・検査・保険・迷いどころまとめ
🚗 特徴的な身体所見と“潜む損傷”のサイン
- シートベルト痕(belt sign):腸管損傷、腹腔内出血 → CTでfree airやfluid確認
- 胸部打撲(ステアリング痕):肋骨骨折、肺挫傷、心タンポナーデ
- 顔面・頸部の外傷:エアバッグ傷、頸椎の過伸展 → 頸椎CT or X線も考慮
- 下肢受傷(バイク・自転車 vs 車):骨盤骨折、大腿骨骨折、股関節脱臼
腹部に帯状の赤い痕があれば、たとえバイタルが安定していても腸管損傷・腹腔内出血の可能性があります。
➡ 躊躇せず腹部CTをオーダーしましょう。
🧠 迷いやすいポイント①:検査をどこまでやるか?
- “軽症に見える”=安全、ではない(特に腹部・骨盤・頸椎)
- 受傷機転+局所の痛み or 所見 → 画像検査を積極的に検討
- CTは医療的に必要なら保険対象。必要あれば撮るべき。
腸管穿孔・膵損傷・腎損傷などは初期症状に乏しく、CTでしか見えないケースも。
特にbelt sign、局所圧痛、SpO₂低下などは赤信号です。
🧾 迷いやすいポイント②:保険と費用の扱い
| 項目 | 対応 |
|---|---|
| 交通事故=自賠責対応 | 加害者側の自賠責保険を通して請求。 事故直後は未確定のことも多いため、一時自費+領収書案内が基本。 |
| 診断書作成 | 「全治日数」は症状の予測期間で記載。実際の障害ではない。 |
| 継続通院の判断 | 軽症でも「整形外科への紹介」などフォローを明示するのが無難。 |
・診断名:「打撲」「挫傷」「捻挫」など具体的に記載
・「骨折はないが痛みあり」→「X線にて骨折は認めず」と書くとトラブル回避に◎
🤔 よくあるケースと現場の判断基準
- 💬 患者「たいしたことない」でも → CTで重大損傷が見つかることはある
- 🚲 自転車 vs 車 → 歩行可でも顔面・歯列・頭部の見落としに注意
- 🚙 軽い追突でも中高年+頸部痛 → 頸椎レントゲン+神経所見確認
D-dimerは骨折そのものではなく、血栓症(DVT/PE)の評価に使う指標。
➡ 骨折疑いにD-dimerは適応外。むしろ骨折後の呼吸苦や下肢腫脹で評価する。
Step 5:特殊症例とよくある骨折
このセクションでは、患者背景によって対応が変わる特殊症例と、救急外来でよく見かける代表的な骨折の診かたを解説します。
5-1. 高齢者・小児・妊婦の外傷対応の注意点
👵 高齢者外傷
- 軽微な外傷でも重症化しやすい(転倒で大腿骨骨折など)
- 抗凝固薬内服 → 軽度の頭部外傷でも出血を伴う可能性あり
- 基礎疾患(心不全・COPDなど)に応じた酸素管理が必要
🧒 小児外傷
- 肝・脾損傷などの腹部損傷が多い(肋骨が柔らかく守られていない)
- 体重が軽くショック進行が早いため、低血糖・低体温にも注意
🤰 妊婦外傷
- 妊娠20週以降では仰臥位低血圧症候群に注意(左側臥位)
- 胎児心拍モニターの設置と産婦人科コンサルトを早期に
- 放射線検査は必要なら実施(母体優先、安全性は比較的高い)
5-2. 救急外来でよく見る骨折の診かた
ここでは、実臨床で「頻度が高く・見逃しやすい」代表的な骨折について、所見と対応を簡潔にまとめます。
🦴 ① 大腿骨頸部骨折(高齢者の転倒で最多)
- 短縮・外旋位をとるのが典型
- X線で見逃すことも → CTやMRIでの精査を考慮
- 早期手術(24~48h以内)がADLと予後改善に有効
🦴 ② Colles骨折(橈骨遠位端骨折)
- 転倒して手をついたときに発生
- 「フォーク状変形(dinner fork deformity)」が有名
- X線で掌側傾斜角と橈骨長が保たれているかを確認
🦴 ③ 上腕骨近位端骨折(elderly+転倒)
- 肩が上がらない/腫脹・変形/外転時痛
- Neer分類で治療方針決定(保存 vs. OP)
- 関節包内骨折 → 出血量に注意
🦴 ④ 脊椎圧迫骨折(圧痛+円背+動作時痛)
- 高齢女性+尻もち → 背部痛・寝返り困難
- X線で明確でないことも → MRIで早期診断
- 急性期は安静+鎮痛/高度変形や遷延で手術考慮
・骨折を見落としやすいタイミング:疼痛訴えが乏しい/X線が正常に見えるとき/“なんとなく動けている”ケース
→ 痛みの局在+介助歩行の可否+圧痛の有無を丁寧に評価しよう。
外傷後の足関節痛に対して、不要なX線撮影を減らすための臨床基準です。次のいずれかを満たす場合は、足関節 or 足部のX線撮影が推奨されます。
- 受傷直後から4歩以上の歩行が困難である
- 外果の後縁〜6cm以内に圧痛がある
- 内果の後縁〜6cm以内に圧痛がある
- 第5中足骨基部に圧痛がある(足部X線)
- 舟状骨に圧痛がある(足部X線)
➡ 上記をすべて満たさなければ、X線を省略できる可能性が高いとされています。
骨盤X線では、以下の順で評価すると見落としが減ります:
- 左右の腸骨翼の高さ・幅の対称性
- 恥骨結合の開大(1cm以上は異常)
- 仙腸関節の開大・不整
- 坐骨・恥骨の骨折線
- アセタブラム(寛骨臼)の整合性
- 骨盤輪の輪郭に途切れがないか
➡「輪郭をなぞるように」丁寧に確認するのがコツです。
Step 5補足:救急外来で見逃さないための外傷ピットフォール&判断のコツ
🧠 小児頭部外傷:CTを撮るべきか?(PECARN+他基準)
小児の頭部外傷に対するCT撮影は、放射線感受性と診断のバランスを取る必要があります。以下の3つの臨床判断基準を組み合わせると安全です。
- PECARN(米):2歳以上/未満で基準が異なる
- CATCH(加):中等度外傷に特化。CT陽性率高い
- CHALICE(英):広範な症状を網羅。感度高め
CT非施行が妥当とされるPECARN(2歳以上)の目安:
- 意識消失がない
- 精神状態に異常がない
- 頭蓋骨骨折の兆候なし
- 激しい受傷機転なし
- 嘔吐が2回未満
- 親が「普段通り」と感じている
・迷うときは複数の基準で確認 → 「すべて満たさなければCTなし」が安心材料に
・保護者説明では以下の数値を活用すると説得力あり:
- 軽症でCT陽性になる確率:約0.5~1.0%
- 重症所見(手術など)の発生率:0.03~0.05%
- 頭部CT 1回の被曝:約2~3 mSv(小児)
🦴 救急外来でよく出会う「その他の外傷」
- 切創・裂創:深さ+腱・神経損傷の確認が大切
- 鼻骨骨折:変形と圧痛が主所見。X線は不要なことも
- Blow-out fracture(眼窩底骨折):複視+頬のしびれ → 顔面CTへ
- 異物刺入(ガラスなど):X線 or エコーで異物確認
- 爆発創・高圧水創:内部損傷、壊死性筋膜炎に注意
・上方視障害/複視/頬のしびれ → 眼窩底骨折を疑う
・“trapdoor型”では筋肉巻き込みで迷走神経反射(嘔吐)を伴うことも
➡ 顔面CT(sagittal)で評価 → 重症例は手術適応あり
🦷 よくある咬傷の初期対応
🧬 種族別|原因菌・抗菌薬・縫合方針のまとめ
① 人咬傷(Human bite)
- 原因菌:Streptococcus属、Staphylococcus aureus、Eikenella corrodens、嫌気性菌
- 抗菌薬:
- 第一選択:アモキシシリン+クラブラン酸
- アレルギー:ドキシサイクリン+メトロニダゾール
- 縫合:原則として開放管理。顔面など整容部位のみ慎重に縫合。
② 犬咬傷(Dog bite)
- 原因菌:Pasteurella canis, Capnocytophaga canimorsus, Staph, Strep, 嫌気性菌
- 抗菌薬:
- 第一選択:アモキシシリン+クラブラン酸
- アレルギー:ドキシサイクリン+メトロニダゾール
- 縫合:中等度の創傷では縫合可。重度汚染や深部損傷では開放管理。
③ 猫咬傷(Cat bite)
- 原因菌:Pasteurella multocida(90%以上)、Fusobacterium、Capnocytophaga、Staph属
- 抗菌薬:
- 第一選択:アモキシシリン+クラブラン酸
- アレルギー:ドキシサイクリン+メトロニダゾール
- 縫合:
原則閉創禁忌。穿通性+嫌気性菌による深部感染リスクのため。
顔面など整容的に重要な部位のみ、洗浄+抗菌薬併用で慎重に縫合を検討。
・小さい創でも、腱鞘・関節包など深部感染に注意
・Pasteurella multocidaは早期発症が多く、炎症所見が軽くても抗菌薬投与+開放管理が基本
④ コウモリ・野生動物咬傷(Bat & Others)
- 主なリスク:狂犬病(Rabies virus)→ 米国ではコウモリ由来が最多
- 抗菌薬:細菌感染にはアモキシシリン+クラブラン酸
- 特殊対応:暴露後ワクチン(PEP)+ヒト免疫グロブリン(HRIG)を適応に応じて実施
- 縫合:原則開放管理。整容的部位は感染管理しつつ縫合可
💉 破傷風ワクチンの確認も忘れずに!
- 咬傷・汚染創では必ず破傷風トキソイド(Td)接種の有無を確認
- 不明 or 10年以上経過 → Td接種を
- 重度汚染創で免疫不明なら Td+TIG(免疫グロブリン)も考慮
「最後に破傷風ワクチン打ったのはいつですか?」を必ず問診で確認。
➡ 小児なら定期接種完了でOK/成人は10年ごとが目安。
次はいよいよ熱傷(Burn)編へと進みます。ここからは、TBSAや深達度分類、補液や吸入傷への対応など、実践的なポイントを体系的に解説していきます。
Step 1:熱傷の基礎知識と重症度評価
熱傷(burns)は、その深達度(burn depth)と熱傷面積(TBSA: Total Body Surface Area)に基づいて評価されます。重症度の判断は、適切な初期対応と入院・紹介の判断に直結するため、正確な評価が求められます。
📌 熱傷の深達度分類(Burn Depth)
- I度熱傷:表皮のみ。紅斑があり、疼痛を伴う。例:日焼け。
- II度熱傷:真皮まで。水疱形成あり。さらに浅達性・深達性に分類。
- III度熱傷:皮下組織に達する壊死性病変。痛みなし(神経も損傷)。皮膚移植の適応。
- IV度熱傷:筋・骨・脂肪組織に及ぶ。極めて重篤。
👉 外観だけでは深達度を即断せず、時間とともに観察が重要です(初期は過小評価しやすい)。
📐 TBSA評価(Rule of 9 & 手掌法)
熱傷面積は成人ではRule of 9が基本で、以下のように身体部位を9%単位で分けて評価します:
- 頭頸部:9%
- 体幹(前面・後面それぞれ):18%
- 上肢(片側):9%
- 下肢(片側):18%
- 会陰部:1%
💡患者の手掌(手のひら+指)を1%として見積もる「手掌法」は小範囲の評価やRule of 9が使いにくい場面で有用です。
📊 熱傷の疫学的特徴(日本国内統計)
- 👶 小児:熱湯や油による家庭内事故が多い
- 👵 高齢者:暖房器具や風呂での低温熱傷が多い
- 🏭 成人:職場や火災事故による重度熱傷の頻度高い
⚠️ 高齢者や小児では、軽度の熱傷でも重症化しやすい点に注意が必要です。
🧪 重症熱傷の定義(参考)
- II度熱傷 ≧ 30%
- III度熱傷 ≧ 10%
- 特殊部位(顔面、手足、会陰、関節部)
- 吸入傷、電撃傷、化学熱傷の合併
➡️ これらに該当する場合は専門施設への紹介・搬送を強く検討します。
Step 2:初期対応と輸液管理(Resuscitation & Initial Management)
重症熱傷では、早期の全身管理が生命予後を左右します。最初の対応は通常の外傷と同様、ABCアプローチに従って評価を進め、その後に熱傷特有の評価と輸液管理を追加します。
🩺 熱傷患者のABCアプローチ
- Airway:顔面熱傷・すす・嗄声・呼吸困難 → 吸入傷疑い
- Breathing:SpO₂低下・呼吸回数増加・肺雑音の聴取
- Circulation:広範囲熱傷で循環血漿量が急激に低下 → ショック徴候に注意
・口腔・鼻腔内にすす/顔面や眉毛の熱傷/喉頭浮腫による嗄声/呼吸困難・咳嗽
→ 早期挿管を検討(躊躇すると困難になる)
💧 輸液管理:パークリンド法(Parkland Formula)
広範囲熱傷では循環血漿量減少性ショックを来すため、早急な輸液が必要です。
計算式:
輸液量(mL)= 4 × 体重(kg) × 熱傷面積(%)
※ 最初の24時間分の輸液量
- 最初の8時間で半量を投与、残りの半量を次の16時間で
- 投与する輸液は乳酸リンゲル液(LR)が第一選択
👉 投与開始は熱傷受傷時からの時間でカウント。来院時に4時間経過していれば、残りの4時間で半量を投与。
📌 輸液開始の基準とモニタリング
- 成人:TBSA 15~20%以上 → 輸液開始
- 小児:TBSA 10%以上 → 早期に輸液開始
- 尿量モニタ:成人 0.5 mL/kg/hr、小児 1.0 mL/kg/hr を目標
- 頻回バイタルチェック、体重、尿量、乳酸、意識レベルなどを定期的に確認
🧑⚕️ 特殊な症例の対応
- 高齢者:基礎疾患・脱水が重なりやすく、低用量から慎重に輸液
- 小児:補正糖(例:5%ブドウ糖加NaK液)の併用が必要なことも
- 電撃傷:表面の熱傷が小さくても、筋壊死・横紋筋融解(rhabdomyolysis)を来すことがあり、尿量確保(1~2 mL/kg/hr)とCK・K値モニタが重要
近年、輸液過剰による「fluid creep」や肺水腫、腹部コンパートメント症候群の報告も増加。
→ 尿量・呼吸状態・腹囲をこまめにチェックし、目標指標に応じた柔軟な調整が求められる。
Step 3:熱傷の初期処置 ― 洗浄・冷却・鎮痛の基本
🔹 1. 初期処置の基本:洗浄と冷却
- 直後の対応:まずは冷水(15〜20℃)で20分程度冷却(やけど直後に限る)。氷水は避ける。
- 創部の洗浄:生理食塩水や流水で異物・壊死組織を除去。優しく行い、感染防止にもなる。
🔹 2. 外用薬とドレッシングの選択
- 非感染創:ワセリンガーゼやハイドロコロイド系の創傷被覆材で湿潤環境を維持。
- 感染が疑われる場合:以下の抗菌外用薬を選択。
- SSD(スルファジアジン銀)軟膏:広域抗菌作用。長期使用で上皮化遅延の可能性があるため、経過を見て変更。
- ソフラチュール(抗菌ガーゼ):非固着性のため、交換時の痛み軽減にも有用。
- ポピドンヨード:広範囲使用は甲状腺機能抑制に注意。
- その他:上皮化促進剤(例:フィブラストスプレー)や、止血・保護目的のフィブリンスプレーは創の状態により選択。ただし感染創には使用不可。
🔹 3. 水疱(Blister)の取り扱い
- 破れていない場合は原則保存。クッション材として機能。
- 感染兆候がある、または大きな張力水疱は、穿刺または除去を考慮。
🔹 4. 鎮痛管理と全身管理
- 鎮痛薬はアセトアミノフェンやNSAIDsから開始。必要に応じてオピオイド。
- 面積が広い場合は、輸液(Parkland formula)や酸素投与を検討。
- 口腔・鼻腔内のスス付着、嗄声がある場合は吸入熱傷を考慮し、早期挿管も視野に。
🔹 5. 感染予防と破傷風対策
- 創感染に注意:特に深達度のある熱傷では嫌気性菌(例:Clostridium属)のリスク。
- 感染兆候(発赤、悪臭、疼痛増悪、発熱)があれば、抗菌薬の全身投与を検討。
- 例)嫌気性菌カバー:アンピシリン・スルバクタムやクリンダマイシン+セフェム系
- 破傷風ワクチン:過去の接種歴に応じてトキソイド投与またはグロブリン併用を考慮。
🔹 6. 小児への対応ポイント
- 体表面積の評価:Lund-Browder表を使用。
- 低血糖とショックに注意:特に2歳未満では補液と栄養管理が重要。
📌 小児・高齢者・特殊部位(顔、関節部、会陰部)などは専門医紹介も早めに検討する。
Step 4:重症度分類と入院・紹介の判断基準
🔸 1. 入院・専門医紹介の適応とは
熱傷の重症度によっては、全身管理や専門的処置(植皮など)が必要になるため、早期の紹介・入院判断が重要です。
📘 Topics|日本での入院・紹介基準の目安
- Ⅱ度熱傷が体表面積(TBSA)30%以上
- Ⅲ度熱傷がTBSA 10%以上
- 特殊部位:顔、手足、会陰部、関節周囲
- 吸入熱傷(嗄声、すす、呼吸障害)
- 電撃傷・化学熱傷(広範囲でなくても)
- 高齢者、小児、基礎疾患あり → 軽症でも慎重に判断
📌 入院が推奨される具体例
- 軽度でも顔・手指・関節など機能重要部位の熱傷
- 疼痛コントロールが難しい症例
- 自宅での処置継続が困難(認知症・独居など)
🔸 2. ABA(American Burn Association)の重症熱傷基準
以下の項目に該当すれば、高次施設への転院・熱傷センターへの紹介が推奨されます。
- Ⅱ度熱傷でTBSAが 10%以上
- Ⅲ度熱傷の存在
- 顔・手・足・会陰・関節周囲の熱傷
- 吸入傷(顔面熱傷、嗄声、呼吸苦、すす)
- 電撃・化学熱傷
- 基礎疾患あり(心不全、糖尿病、精神疾患など)
🧮 Burn Index(BI)と Prognostic Burn Index(PBI)
- Burn Index (BI):
BI = Ⅲ度熱傷面積(%) + Ⅱ度熱傷面積(%) ÷ 2 - Prognostic Burn Index (PBI):
PBI = BI + 年齢
👉 PBI > 100:予後不良(致死率高)
BIだけではわからない高齢者の重症度を把握可能。
→ PBIは特に紹介や搬送判断の参考になる!
🧠 心理的ケアの視点も忘れずに
- 顔面熱傷や若年女性では精神的ダメージ大 → 早期の精神面ケアも考慮
- 小児は外傷後ストレス障害(PTSD)のリスクあり
🗣️ 外傷・熱傷に役立つMedical English集(英語表現・略語・発音)
📘 1. 基本用語・略語(Glossary)
■ 熱傷(Burns)
- Burn:熱傷
- Scald:熱湯熱傷
- TBSA:Total Body Surface Area(熱傷面積)
- Parkland formula:パークリンド法
- Graft / Grafting:皮膚移植
- Inhalation injury:吸入傷
- Debridement:デブリードマン(壊死組織除去)
■ 外傷(Trauma)
- Fracture:骨折
- Laceration:裂創
- Contusion:打撲
- Open fracture / Closed fracture:開放骨折/閉鎖骨折
- Spinal injury:脊椎損傷
- Seatbelt sign:シートベルト痕
- Pneumothorax:気胸
📑 2. よく使う英語表現(Expressions)
- “The burn covers about 20% of his total body surface area.”
- “Let’s start fluid resuscitation using the Parkland formula.”
- “She has a displaced distal radius fracture.”
- “There is a large laceration that may require suturing.”
- “He has difficulty moving his legs, suspect spinal injury.”
- “Signs of inhalation injury include hoarseness and facial burns.”
👄 3. 発音注意!(Common Mistakes)
- Debridement:×デブリードマン → ○【dəˈbridmənt】(デブリードメント)
- Graft:○【ɡræft】(グラフト)
- Contusion:○【kənˈtuːʒən】(カントゥージョン)
- Inhalation:○【ˌɪnhəˈleɪʃən】(インハレイション)
🧍 4. Layman’s 用語(患者・家族への説明)
- “The bone is broken but didn’t break the skin.”(骨は折れましたが、皮膚には傷がありません)
- “This burn is deep and may need a skin graft.”(熱傷が深く、皮膚移植が必要かもしれません)
- “We need to stitch the wound to stop the bleeding.”(止血のため縫合が必要です)
- “You’ll need to stay in the hospital for treatment.”(入院が必要です)
📘 記事全体のまとめ
外傷と熱傷は、救急外来で日常的に遭遇するものですが、重症例や見逃してはいけない病態も多く含まれています。
本記事では、初期対応・重症度評価・処置・紹介判断に至るまで、実際の臨床に即した形で体系的に整理しました。
- 🚑 まずはABCDアプローチと安全確保
- 🦴 外傷では骨折・打撲・裂創の見極めがカギ
- 🔥 熱傷では深達度・TBSAの評価が基本
- 💧 パークリンド法などによる輸液管理の実践力
- 📈 BIやPBIを使った重症度と予後の評価
- 🤝 迷ったら早期の紹介・専門医連携を
👉 本記事が、救急現場での冷静な判断・安全な処置・適切な紹介の一助となれば幸いです。
🔗 関連する症候別記事リンク
📚 Reference(参考文献)
- Complete Trauma & Burn Manual(2024年版)
- Trauma and Burn Management Summary
- 日本熱傷学会ガイドライン(2020年度改訂)
- 日本救急医学会 外傷初期診療コースJATEC資料
- American Burn Association Guidelines
- PECARN head CT rule (Kuppermann N, 2009)
- Ottawa Ankle Rules(Stiell IG et al. 1992)